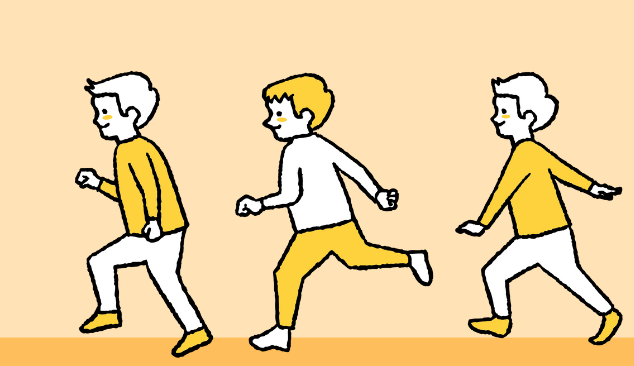はじめに
近年、子育てをする家庭にとって「認定こども園」という言葉を耳にする機会が増えてきました。しかし、その具体的な内容や保育園、幼稚園との違いについてはあまり知られていないかもしれません。本記事では、認定こども園の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。
認定こども園とは
認定こども園は、2006年に創設された新しい形の保育施設です。幼稚園と保育園の機能を併せ持ち、教育と保育の両方を提供する施設として位置づけられています。
認定こども園は「幼保一元化」という政府の政策によってつくられた施設で、さまざまな保育ニーズに対応し、保育の受け入れ幅を広げることを目的としています。
認定こども園ができた理由・目的・役割
認定こども園は、以下のような背景や目的から設立されました。
- 保育ニーズの多様化:共働き家庭の増加に伴い、長時間保育が必要な子どもが増えたため。
- 教育・保育の一体化:幼稚園と保育園の役割を融合させることで、子どもの一貫した成長支援を目指すため。
- 地域の子育て支援:地域社会における子育て支援拠点としての役割も果たすため。
上記の問題を解消すべく考えられたのが、「幼保一元化」政策です。
これまで、保育園には共働きの世帯しか入園できず、幼稚園では就労している親には保育時間が足りないという問題がありました。
そのため、保育園や幼稚園を認定こども園に変えていくことで、それぞれの入園条件を緩和し、こどもの受け入れ幅を広げることが、認定こども園の主な目的です。
認定こども園の3つの特徴
認定こども園には、他の保育施設とは異なる独自の特徴がいくつかあります。
特徴①:保育と教育を同時に行う
認定こども園は、保育園の保育機能と幼稚園の教育機能を兼ね備えています。これにより、0歳から就学前までのこどもが一貫して質の高い教育・保育を受けることが可能です。
また、以下の機能を備えている必要があります。
- 就労の有無に関係なくこどもの受け入れや教育を行う
- 保育を一体的に実施できること
- すべての子育て家庭を対象に、子育て相談や親子が集う場所の提供を行う
これらの条件を満たした保育園・幼稚園は都道府県から認定を受けることで、認定こども園となることができます。
認定された保育施設には、保育の質の向上のため年一回の自己点検・自己評価の提出が求められています。
特徴②:「保育教諭」の配置が必須
認定こども園では、幼稚園教諭と保育士の両方の資格を持つ「保育教諭」を配置することが義務付けられています。これにより、こどもたちは専門的な教育と保育を受けることができます。
特徴③:子どもの受け入れ幅が広い(保護者は選択肢が増える)
認定こども園は、0歳から5歳までの幅広い年齢のこどもを受け入れます。また、これまでよりも入園の際の制限が減り、より多くのこどもを受け入れられるようになりました。
これにより、保護者は、「就労している→保育園」「専業主婦→幼稚園」といった型にはまることなく預け先を選ぶことが可能になり、仕事や生活スタイルに合わせて柔軟に施設を選択することができます。
認定こども園には4つの種類がある
認定こども園は、運営形態によって4つのタイプに分類されます。それぞれのタイプについて詳しく見ていきましょう。
種類①:幼保連携型
幼保連携型認定こども園は、幼稚園と保育園の機能を一体的に運営する施設です。教育と保育を一体的に提供し、長時間保育にも対応します。
幼保連携型認定こども園では、保育時間は1日8時間、11時間開園、土曜日の開園が原則となっています。
種類②:幼稚園型
幼稚園型認定こども園は、主に私立や公立の認可幼稚園に、保育所的な機能を追加した施設です。幼稚園では、これまでこどもを預かる時間が4時間と決められていました。しかし、認定こども園となることで、両親の就労状況に応じて8~11時間の預かりが可能となったため、就労している保護者でも預けられるようになりました。教育が中心となりますが、保育のニーズにも応えます。
種類③:保育所型
保育所型認定こども園は、主に公立や私立の認可保育園に、幼稚園的な教育内が容追加された施設です。認定こども園となることで、就労していない保護者も利用が可能になります。(※1号認定 3歳以上で保育の必要性がないこどもが対象。)1号認定以外のこどもが利用する場合は、園に直接申し込む必要があります。基本的には、保育所保育指針に基づき、保育を行います。
種類④:地方裁量型
地方裁量型認定こども園は、自治体の裁量によって認可外保育園や幼稚園を認定こども園と認めた保育施設となり、地域の特性やニーズに応じて運営される施設です。地方裁量型認定こども園は、採用していない自治体が多く、数が少ないのが現状です。
「保育園・幼稚園」と「認定こども園」の機能面での違い
認定こども園と保育園、幼稚園は、それぞれ異なる役割と機能を持っています。
保育園は【保育】を提供
保育園は、共働き家庭や育児に支援が必要な家庭のこどもを対象に、長時間の保育を提供します。主に0歳から5歳までのこどもが対象で、保育が中心です。
幼稚園は【教育】を提供
幼稚園は、主に3歳から5歳までのこどもを対象に、教育を中心に提供します。就学前の準備としての教育プログラムが重視されます。
「保育園・幼稚園」と「認定こども園」の保育料の違い
保育料についても、認定こども園、保育園、幼稚園それぞれに違いがあります。
【認定こども園】保育料
認定こども園の保育料は、自治体ごとに異なりますが、家庭の所得状況やこどもの年齢によって決定されます。3歳以上は保育料無償化の対象であり、保育料はかかりません。長時間保育と教育の両方が提供されるため、費用対効果の高い選択肢となることが多いです。
【保育園】保育料
保育園の保育料も、自治体ごとに異なります。家庭の所得状況やこどもの年齢によって決定され、長時間保育が必要な場合は追加料金が発生することもあります。
3歳以上は保育料無償化の対象となります。
【幼稚園】保育料
幼稚園の保育料は、主に私立の場合は比較的高額になることが多いです。しかし、公立の幼稚園の場合は、比較的安価な場合もあります。教育が中心のため、追加の費用が発生することもあります。3歳以上は保育料無償化の対象となります。
認定こども園を利用するときに知っておきたい「認定区分」
認定こども園を利用する際には、こどもと家庭の状況に応じて「認定区分」があります。以下の3つの認定区分があります。
1号認定
1号認定は、保育を必要としない3歳から5歳のこどもが対象です。主に幼稚園型認定こども園を利用する場合に適用されます。
2号認定
2号認定は、保育を必要とする3歳から5歳のこどもが対象です。保育所型や幼保連携型認定こども園を利用する場合に適用されます。
3号認定
3号認定は、保育を必要とする0歳から2歳のこどもが対象です。主に保育所型認定こども園を利用する場合に適用されます。
保護者は就労状況などから保育施設を選択しましょう
認定こども園をはじめ、保育園や幼稚園などの選択肢が増える中で、保護者は自分の就労状況やこどもの年齢、保育ニーズに応じて適切な施設を選択することが重要です。自治体の支援制度や施設の特徴をよく理解し、最適な保育環境を提供しましょう。
まとめ
認定こども園は、保育園と幼稚園の良いところを併せ持つ新しい形態の保育施設です。保育と教育を同時に受けることができるため、こどもの成長にとって非常に有益です。保護者にとっても選択肢が広がり、柔軟な対応が可能になります。本記事を参考に、認定こども園の利用を検討してみてください。