
赤ちゃんの離乳食が進むと、「スプーンの練習はいつから始めたらいいの?」「正しい持ち方はどうやって教えるの?」と気になるママ・パパも多いのではないでしょうか。周りの子と比べて焦ってしまったり、うまくできなくて悩んだりすることもあるかもしれません。
この記事では、スプーンの持ち方を練習する時期の目安から、発達段階に合わせた3つのステップ、親子で楽しく取り組める練習方法まで、詳しく解説します。この記事を読めば、お子さんのペースに合わせたスプーン練習の進め方が分かり、自信を持ってサポートできるようになりますよ。
目次
- 1. 赤ちゃんのスプーンの持ち方、焦らなくて大丈夫!
- 1-1. スプーンの上達には個人差がある
- 1-2. 無理強いはNG!食事の時間を楽しいものに
- 2. スプーン練習はいつから始める?目安となる3つのサイン
- 2-1. サイン1:食べ物に興味を示し、手を伸ばす
- 2-2. サイン2:大人の真似をしてスプーンを持ちたがる
- 2-3. サイン3:お座りが安定して両手が使える
- 3. 【発達段階別】スプーンの持ち方3ステップ完全ガイド
- 3-1. ステップ1(1歳前後):上手持ち(グー握り)
- 3-2. ステップ2(1歳半〜2歳頃):下手持ち(指先握り)
- 3-3. ステップ3(2歳半〜3歳頃):鉛筆持ち(三点持ち)
- 4. 【遊び感覚でOK】親子で楽しくできるスプーン練習方法
- 4-1. 食事以外の時間でできる!指先を鍛える遊びリスト
- 4-2. まずはママ・パパがお手本を見せよう
- 4-3. 「すくう→運ぶ→口に入れる」を分解して練習
- 4-4. 食べこぼしは成長の証!汚れてもいい環境づくり
- 5. スプーン練習あるあるQ&A|下手持ち・遊び食べの対処法
- 5-1. Q. 上手持ち(グー握り)がなかなか直りません。どうすればいいですか?
- 5-2. Q. スプーンで遊び食べばかりしてしまいます。
- 5-3. Q. 左手で持ちたがるけど、利き手はどちらにすべき?
- 5-4. Q. フォークはいつから練習すればいいですか?
- 6. もう迷わない!練習用スプーン・フォークの選び方3つのポイント
- 6-1. ポイント1:子どもの手の発達に合った「形」と「素材」
- 6-2. ポイント2:自分で「すくいやすい」「刺しやすい」工夫があるか
- 6-3. ポイント3:食洗機対応など「お手入れのしやすさ」も重要
- 7. 【保育士に聞く】保育園入園までにスプーンはどこまでできればいい?
- 7-1. 結論:完璧にできなくても大丈夫!
- 7-2. 保育園ではどんな風に食事のサポートをしてくれるの?
- 7-3. 家庭でできる入園準備とは?
- 8. まとめ:子どものペースでスプーンの持ち方をマスターしよう
- 9. 保育園での生活が気になったら
1. 赤ちゃんのスプーンの持ち方、焦らなくて大丈夫!
まず一番にお伝えしたいのは、赤ちゃんのスプーンの持ち方について、焦る必要は全くないということです。食事は本来、楽しい時間であるべき。保護者の焦りは赤ちゃんにも伝わってしまい、食事が嫌いになるきっかけにもなりかねません。
1-1. スプーンの上達には個人差がある
スプーンを上手に使えるようになる時期は、本当に人それぞれです。手先の発達や食べ物への興味の度合いによって、早くから上達する子もいれば、ゆっくり自分のペースで習得していく子もいます。
大切なのは、周りの子と比べるのではなく、昨日のお子さんより少しでも成長した点を見つけて褒めてあげることです。「スプーンを握れたね」「自分で口に運ぼうとしたね」など、小さな「できた!」を一緒に喜んであげましょう。
1-2. 無理強いはNG!食事の時間を楽しいものに
「こう持たなきゃダメ!」と厳しく教えたり、無理にスプーンを持たせたりするのは逆効果です。赤ちゃんが「食事=楽しくない時間」と感じてしまうと、スプーン練習どころか、食べること自体に消極的になってしまう可能性があります。
まずは「自分で食べたい」という気持ちを育てることが最優先です。手づかみ食べも、食べこぼしも、すべてが大切な成長の過程。温かく見守りながら、食事の時間が親子にとって楽しいひとときになるような雰囲気作りを心がけましょう。
2. スプーン練習はいつから始める?目安となる3つのサイン
では、具体的にスプーンの練習はいつから始めれば良いのでしょうか。月齢で区切るのではなく、お子さんの様子から見える以下の3つのサインを目安にしてみてください。
2-1. サイン1:食べ物に興味を示し、手を伸ばす
離乳食を目の前にしたとき、赤ちゃんが身を乗り出したり、「あー、うー」と声を出しながら食べ物に手を伸ばしたりするようになったら、それは「自分で食べたい」という意欲の表れです。この興味の芽を逃さず、スプーン練習を始める良いタイミングと捉えましょう。
2-2. サイン2:大人の真似をしてスプーンを持ちたがる
ママやパパがスプーンで食事をしている様子をじっと見て、真似をしようとしたり、スプーンを取りたがったりするしぐさが見られたら、絶好のチャンスです。大人の行動を模倣するのは、赤ちゃんが成長している証拠。安全な赤ちゃん用のスプーンを渡して、まずは自由に触らせてあげましょう。
2-3. サイン3:お座りが安定して両手が使える
腰がしっかりと座り、両手を自由に使えるようになることも大切なポイントです。安定した姿勢で座れると、食べ物に集中し、手を使ってスプーンを操作しやすくなります。離乳食中期(7〜8ヶ月頃)から後期(9〜11ヶ月頃)にかけて、お座りが上手になってきたら、スプーン練習を意識し始めると良いでしょう。
3. 【発達段階別】スプーンの持ち方3ステップ完全ガイド
赤ちゃんのスプーンの持ち方は、手の筋肉や指先の機能の発達とともに、段階的に変化していきます。ここでは、一般的な発達の流れに沿った3つのステップをご紹介します。
3-1. ステップ1(1歳前後):上手持ち(グー握り)
- 持ち方の特徴
- 手のひら全体でスプーンの柄を上から鷲掴みにするように握る持ち方です。「上手持ち(うわてもち)」や「グー握り」と呼ばれます。赤ちゃんが最初にスプーンを持つとき、自然とこの形になります。
- サポートのポイント
- この段階では、まだ手首を返す動きが難しいため、すくった食べ物をこぼさずに口へ運ぶのは至難の業です。ママ・パパが手を添えてサポートしたり、すくいやすいように少し深さのあるお皿を使ったりする工夫がおすすめです。まずは「スプーンで食べ物に触れる」「握る」という感覚に慣れることが目標です。
3-2. ステップ2(1歳半〜2歳半頃):下手持ち(指先握り)
- 持ち方の特徴
- スプーンの柄を下から握る持ち方です。「下手持ち(したてもち)」や「指先握り」と呼ばれます。指先が少しずつ使えるようになり、上手持ちよりもスプーンの角度を調整しやすくなります。
- サポートのポイント
- 下手持ちになると、手首を使ってスプーンを口に運びやすくなり、自分で食べられる量が増えてきます。スプーンの先に食べ物を乗せてあげて、「こうやってすくうんだよ」と見せてあげましょう。まだまだ食べこぼしは多い時期ですが、自分で食べる喜びを感じられるよう、たくさん褒めてあげてください。
3-3. ステップ3(3歳〜4歳頃):鉛筆持ち(三点持ち)
- 持ち方の特徴
- 親指、人差し指、中指の3本で、鉛筆を持つようにスプーンを支える、大人と同じ持ち方です。「鉛筆持ち(えんぴつもち)」や「三点持ち」と呼ばれます。指先を器用に使えるようになり、食べ物をこぼさずに口へ運べるようになります。
- サポートのポイント
- この持ち方ができるようになるには、指先の細かい動きが必要です。なかなか移行できない場合は、焦らずステップ2の下手持ちで十分です。食事以外の遊びで指先を使う経験を増やすことも、鉛筆持ちへの移行を助けます。正しい持ち方ができたら、「持ち方上手だね!」と具体的に褒めてあげると、子どもの自信につながります。
4. 【遊び感覚でOK】親子で楽しくできるスプーン練習方法
スプーン練習は、食事の時間だけがすべてではありません。遊びを通して指先の器用さを育むことで、自然とスプーン操作も上手になります。
4-1. 食事以外の時間でできる!指先を鍛える遊びリスト
- 粘土遊び:こねる、ちぎる、丸めるなどの動作が指先の力を育てます。
- シール貼り:台紙からシールを剥がし、好きな場所に貼る作業は、指先の集中力と調整力を高めます。
- お絵描き:クレヨンや太めのペンを握って描くことで、自然と「持つ」練習になります。
- つまむ遊び:ティッシュを丸めたものや綿などを、お皿からお皿へ移す遊びもおすすめです。
4-2. まずはママ・パパがお手本を見せよう
子どもは、大人の真似をする天才です。食事のとき、向かい合って座り、「こうやってすくって、あーん、おいしいね」と、楽しそうに食べる様子を見せてあげましょう。正しい持ち方をゆっくりと見せることで、子どもは自然とそれを真似しようとします。
4-3. 「すくう→運ぶ→口に入れる」を分解して練習
一連の動作を一度にやろうとすると、赤ちゃんにとってはとても難しいものです。
- すくう:ママ・パパがスプーンに食べ物を乗せてあげる。
- 運ぶ:赤ちゃんが自分でスプーンを持って口まで運ぶ。(最初は手を添えてサポート)
- 口に入れる:自分で口に入れて食べる。
このように動作を分解し、一つずつ「できた!」を積み重ねていくことで、赤ちゃんの成功体験となり、やる気につながります。
4-4. 食べこぼしは成長の証!汚れてもいい環境づくり
スプーン練習に食べこぼしはつきものです。床に新聞紙やレジャーシートを敷いたり、汚れてもすぐに着替えられる服を用意したり、袖が汚れにくい食事用エプロンを活用したりと、汚れてもママ・パパがイライラしない環境を整えることが、実はとても重要です。おおらかな気持ちで見守ることが、子どもの「自分でやりたい」気持ちを後押しします。
5. スプーン練習あるあるQ&A|下手持ち・遊び食べの対処法
ここでは、保護者の方からよくいただくスプーン練習に関する質問にお答えします。
5-1. Q. 上手持ち(グー握り)がなかなか直りません。どうすればいいですか?
A. 焦る必要はありません。まずはその持ち方で上手に食べられることを目指しましょう。
上手持ちから鉛筆持ちへの移行には、指先の発達が必要です。2歳を過ぎても上手持ちが続く場合でも、まずはその持ち方で食べ物をこぼさず口に運べるようになることが大切です。無理に持ち方を矯正するより、前述したような指先を使う遊びを取り入れながら、発達を気長に待ってあげましょう。
5-2. Q. スプーンで遊び食べばかりしてしまいます。
A. 食事の時間を区切る、一度お皿を下げるなどの対応を試してみましょう。
お腹がいっぱいになったり、食事に飽きたりすると、スプーンでお皿を叩いたり、食べ物を混ぜたりする「遊び食べ」が始まることがあります。これは食べ物への好奇心の表れでもありますが、食事のマナーを教える機会でもあります。「ごちそうさまかな?」と声をかけ、食事を切り上げるルールを少しずつ作っていくと良いでしょう。
5-3. Q. 左手で持ちたがるけど、利き手はどちらにすべき?
A. 3歳頃までは、子どもが持ちやすい方の手で持たせてあげましょう。
赤ちゃんのうちは、まだ利き手が定まっていません。両方の手を同じように使う時期なので、本人が持ちやすい手で自由に練習させてあげて問題ありません。無理に右手で持たせようとすると、食事への意欲が削がれてしまうこともあります。自然と使いやすい手が決まってくるのを待ちましょう。
5-4. Q. フォークはいつから練習すればいいですか?
A. スプーンに慣れてきて、自分で刺して食べたがるようになったら始めどきです。
一般的には、1歳半頃からフォークを使い始める子が多いです。スプーンで「すくう」より、フォークで「刺す」方が簡単な場合もあります。お子さんがフォークに興味を示したら、まずはバナナや蒸しパンなど、柔らかくて刺しやすいものから試してみましょう。
6. もう迷わない!練習用スプーン・フォークの選び方3つのポイント
赤ちゃんの「自分で食べたい!」をサポートするために、使いやすい道具選びも重要です。練習用のスプーンやフォークを選ぶ際の3つのポイントをご紹介します。
6-1. ポイント1:子どもの手の発達に合った「形」と「素材」
- 形:持ち手が太く、短く、滑りにくいものがおすすめです。まだ握る力が弱い赤ちゃんでも、しっかりと握ることができます。
- 素材:口に入れても安全なプラスチックやシリコン製が一般的です。金属製のものは、歯や歯茎を傷つける可能性があるので、もう少し大きくなってからが良いでしょう。
6-2. ポイント2:自分で「すくいやすい」「刺しやすい」工夫があるか
- すくいやすさ:スプーンの先端(皿の部分)が平らだったり、少し角度がついていたりすると、食べ物をすくいやすくなります。
- 刺しやすさ:フォークの先端は、安全のために丸くなっていますが、溝がついていて麺類が絡みやすい工夫がされているものもあります。
6-3. ポイント3:食洗機対応など「お手入れのしやすさ」も重要
毎日のことなので、お手入れのしやすさも大切なチェックポイントです。食洗機に対応しているか、パーツが少なく洗いやすいかなども確認しておくと、ママ・パパの負担が軽くなります。
| ポイント | チェック項目 |
|---|---|
| 形・素材 | ・持ち手は太く短いか ・滑りにくい素材か ・口に入れても安全な素材か |
| 使いやすさ | ・すくいやすい角度や形になっているか ・刺しやすい、麺が絡みやすい工夫があるか |
| 手入れ | ・食洗機に対応しているか ・洗いやすい構造か |
7. 保育園入園までにスプーンはどこまでできればいい?
育休が明けて職場復帰を控えている方にとって、「入園までにスプーンは完璧に使えるようにならないとダメ?」という不安は大きいですよね。
7-1. 結論:完璧にできなくても大丈夫!
安心してください。入園時にスプーンが上手に使えなくても全く問題ありません。
保育園では、一人ひとりの発達段階に合わせて、食事のサポートを丁寧に行います。まだ手づかみ食べが中心の子、スプーンを練習中の子、フォークを使い始めた子など、クラスには様々な発達段階の子どもたちがいます。私たちは、その子に合った方法で「自分で食べる」楽しさを感じられるよう援助していきます。
7-2. 保育園ではどんな風に食事のサポートをしてくれるの?
保育園では、家庭と同じように、またはそれ以上にきめ細やかなサポートを心がけています。
例えば、
- スプーンを持ちたがらない子には、まず保育士が食べさせてあげて安心感を与える
- 上手持ちの子には、手を添えて口まで運ぶのを手伝う
- 少しでも自分で食べられたら、「すごいね!」「おいしいね!」とたくさん褒めて意欲を引き出す
など、その子の状況に応じて対応を変えています。集団生活の中で、お友達が食べている様子を見て刺激を受け、急にやる気を出す子もたくさんいますよ。
7-3. 家庭でできる入園準備とは?
入園に向けてご家庭でできる一番大切な準備は、「食事は楽しい時間」という経験をたくさんさせてあげることです。持ち方を教えることよりも、親子で食卓を囲み、「おいしいね」と笑い合う時間を大切にしてください。その楽しい記憶が、保育園での新しい生活をスムーズにスタートさせる土台になります。
8. まとめ:子どものペースでスプーンの持ち方をマスターしよう
今回は、赤ちゃんのスプーンの持ち方について、練習を始めるサインから発達段階別のステップ、具体的な練習方法まで解説しました。
- スプーン練習は焦らず、子どもの「食べたい」気持ちを尊重する
- 練習開始の目安は「興味」「模倣」「安定したお座り」の3サイン
- 「上手持ち」→「下手持ち」→「鉛筆持ち」と段階的に発達する
- 遊びを通して指先を鍛え、汚れてもいい環境で楽しく練習する
- 保育園入園までに完璧にできなくても大丈夫!
スプーンの持ち方をマスターするまでの道のりは、子どもの成長を間近で感じられる貴重な時間です。周りと比べず、お子さん自身のペースを大切に、親子で楽しく食事の時間を過ごしてくださいね。
9. 保育園での生活が気になったら
「保育園ではどんな食事を出してくれるのかな?」「アレルギー対応は大丈夫?」など、保育園での生活について具体的に気になり始めたら、園探しをスタートするタイミングかもしれません。
保育園探しなら「エンクル」が便利です。お住まいの地域の保育園を検索し、食事の方針や園の雰囲気もチェックできます。見学予約もサイトから簡単に行えるので、保活の第一歩としてぜひご活用ください。
- STEP1 園を探す
地図や地域、こだわりの条件から希望に合った保育園を簡単に探せます。 - STEP2 園を比較する
お気に入り登録した園の情報を一覧で比較検討できます。 - STEP3 園を見学予約する
気になる園が見つかったら、サイトからすぐに見学予約が可能です。 - STEP4 園を見学する
見学で気づいたことは「見学日記」に記録して、後から見返せます。 - STEP5 比較・共有する
見学日記の内容は、家族と簡単にシェアして相談できます。 - STEP6 園を決定する
比較検討して、お子さんにぴったりの園を決定しましょう。
理想の保育園・幼稚園探しなら「エンクル」 検索して地図上で空き情報を一括比較!口コミや見学予約機能も。登録した希望条件でオファーも届く!
保育園探しはプロにお任せ!希望の園探しをトコトンお手伝いします!
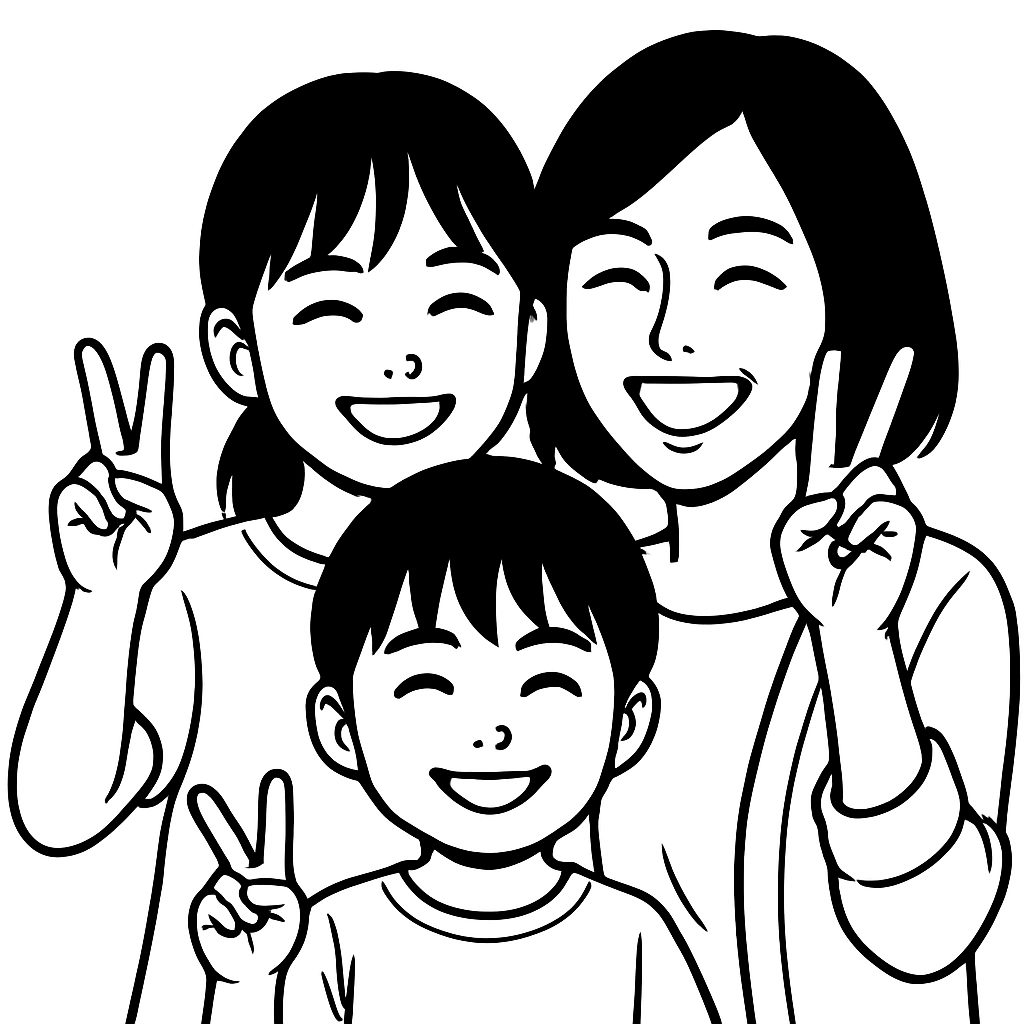
保活アドバイザーのもっちゃんです。小3の娘と年少の息子を育てる2児の母。保育園の転園を経験し、実体験をもとに保活&子育て情報を発信中。癒しは愛猫とのまったり時間です。









