
「毎晩のように続く子どもの夜泣きで、心身ともに疲れ果ててしまう…」
「もうすぐ仕事復帰なのに、このままじゃ体力がもたない…」
子どもの夜泣きは、多くのパパやママが直面する大きな悩みのひとつです。特に、1歳を過ぎ、2歳、3歳と成長するにつれて夜泣きの原因も変化するため、どう対応すれば良いのか分からなくなってしまうことも少なくありません。
この記事では、子どもの月齢別に夜泣きの主な原因と、今日から実践できる具体的な対策を詳しく解説します。夜泣きのメカニズムを理解し、適切なケアを行うことで、親子の睡眠の質を改善するお手伝いができれば幸いです。
目次
- 1. 2歳児の夜泣きが止まらない理由とその対処法
- 2. 3歳児の夜泣きはもう遅い?今からでもできるケア
- 3. 1歳児の夜泣きに向き合うための基本情報
- 4. 新生児期の夜泣きはいつまで続く?新米パパママへのアドバイス
- 5. 8ヶ月赤ちゃんの夜泣きが激しいときに試したいこと
- 6. 7ヶ月赤ちゃんが急に夜泣きを始めたらどうする?
- 7. 9ヶ月赤ちゃんと6ヶ月赤ちゃんで異なる夜泣き対策
1. 2歳児の夜泣きが止まらない理由とその対処法
2歳頃になると、言葉も増え、自我が芽生えてくる大切な時期です。しかし、その成長が夜泣きの原因になることも。特に保育園入園を控えているなど、生活環境の変化が近づいている場合は、子どもも無意識に不安を感じているのかもしれません。
1-1. 2歳児の夜泣きの原因とその特徴
- 言葉や感情の発達によるストレス
- 2歳頃は「イヤイヤ期」とも重なり、自分の気持ちをうまく言葉で表現できないもどかしさから、日中にストレスを溜め込んでしまうことがあります。その日の出来事や感情が夢に出てきて、混乱して泣き出してしまう「夜驚症(やきょうしょう)」のような症状が見られることもあります。
- 不安感や環境変化への敏感さ
- 記憶力が発達し、怖い夢を見ることも増えてきます。また、弟や妹が生まれる、引っ越し、保育園への入園など、生活環境の変化に敏感に反応し、不安から夜中に目を覚ましてしまうことがあります。
1-2. 親ができる夜泣き対策の実践方法
2歳児の夜泣き対応のポイントは「安心感」です。理屈で言い聞かせるよりも、まずは子どもの気持ちに寄り添い、不安を取り除いてあげることが大切です。
- 抱っこや声かけで安心感を与える
「大丈夫だよ」「ママ(パパ)はここにいるよ」と優しく声をかけ、背中をトントンしたり、ぎゅっと抱きしめてあげましょう。子どもの存在を肯定し、気持ちを受け止める姿勢が安心に繋がります。 - リラックスできる寝室環境を整える
寝る前に興奮させすぎないよう、テレビやスマートフォンは早めに切り上げ、穏やかな音楽を聴いたり、絵本を読んだりする時間を設けましょう。お気に入りのぬいぐるみやタオルを側に置くのも効果的です。
2. 3歳児の夜泣きはもう遅い?今からでもできるケア
「もう3歳なのに夜泣きが治まらない…」と心配になるかもしれませんが、決して遅すぎることはありません。3歳児の夜泣きには、2歳までとはまた違った原因が考えられます。生活習慣を見直すことで改善されるケースも多くあります。
2-1. 3歳児の夜泣きはなぜ起こるのか
- 日中の活動量不足による影響
- 3歳になると体力がさらについてきます。天気が悪くて外で遊べなかった日など、体力が有り余っていると寝つきが悪くなったり、夜中に目を覚ましやすくなったりします。
- 睡眠習慣や生活リズムの乱れ
- 昼寝の時間が長すぎたり、夕方近くまで寝てしまったりすると、夜の睡眠に影響が出ます。また、就寝時間が日によってバラバラだと、体内時計が乱れてしまい、質の良い睡眠が取りにくくなります。
2-2. 適切な睡眠環境づくりで夜泣きを減らそう
3歳児には、質の良い睡眠をとるための生活リズムを親子で一緒に作っていくことが効果的です。
- 寝室を暗く静かに保つ工夫
豆電球などの小さな光でも睡眠の質を下げることがあります。できるだけ真っ暗な環境を整えましょう。遮光カーテンの利用もおすすめです - 日中に体を動かす時間を増やす
午前中に公園で思いっきり走ったり、お散歩の距離を少し伸ばしたりするなど、意識的に体を動かす時間を作りましょう。「適度な疲れ」が良い睡眠を促します。
3. 1歳児の夜泣きに向き合うための基本情報
1歳は、赤ちゃんの時期から少しずつ幼児へと成長していく過渡期です。心も体も大きく発達するこの時期の夜泣きには、特有の理由があります。
3-1. 1歳児特有の夜泣きパターンを知ろう
- 睡眠サイクルが未成熟なため起こる覚醒
- 大人は深い眠りと浅い眠りを繰り返しますが、1歳頃の子どもはまだこの睡眠サイクルが安定していません。浅い眠りに入ったタイミングで、ささいな物音や不快感で目を覚ましてしまいやすいのです。
- 分離不安による夜泣き
- ママやパパが視界からいなくなると強い不安を感じる「分離不安」がピークを迎える時期です。夜中にふと目を覚ましたとき、隣に誰もいないことに気づいて不安で泣き出してしまいます。
3-2. 夜泣きを軽減するためのルーティン作り
1歳児の夜泣き対策で最も大切なのは、「これから寝る時間だ」という心構えをさせてあげることです。毎日の「入眠儀式」を作り、生活リズムを整えましょう。
- 寝る前に絵本や子守唄でリラックスさせる
お風呂から出たらパジャマに着替え、照明を少し落とした部屋で絵本を読む、静かな子守唄を歌うなど、寝る前の行動を毎日同じパターンにすることで、子どもは自然と眠る準備に入れます。 - 毎日の就寝時間を一定に保つ
休日も平日と大きく生活リズムを変えず、できるだけ同じ時間に布団に入るように心がけましょう。体内時計が整い、決まった時間に眠気を感じるようになります。
4. 新生児期の夜泣きはいつまで続く?新米パパママへのアドバイス
生まれたばかりの赤ちゃんが夜中に泣くのは、ごく自然なことです。昼夜の区別がまだついておらず、生理的な欲求を伝える唯一の手段が「泣くこと」だからです。
4-1. 新生児の夜泣きはどうして起こる?
- 生理的な要因(お腹が空いた、オムツ交換など)
- 新生児は胃が小さいため、一度にたくさんのミルクやおっぱいを飲むことができません。そのため、2~3時間おきにお腹が空いて目を覚まします。また、おむつが濡れた不快感で泣くこともよくあります。
- 環境適応による不安感
- ママのお腹の中から外の世界に出てきたばかりの赤ちゃんは、物音や光、温度の変化など、あらゆる刺激に不安を感じています。ママやパパに抱っこされることで安心し、眠りにつくことができます。
4-2. 新生児期に親ができるサポートとは?
- 授乳やおむつ替えで適切に対応する
- まずは赤ちゃんが何を求めているのかを確認しましょう。お腹が空いていないか、おむつは汚れていないか、暑すぎたり寒すぎたりしないかなど、不快の原因を取り除いてあげることが基本です。
- 親自身も休息を取れる環境を整える
-
この時期、最も大切なのはパパとママが無理をしすぎないことです。赤ちゃんが寝ている間に一緒に仮眠をとる、家事を完璧にこなそうとしないなど、意識的に休息時間を確保しましょう。夫婦で協力し、交代で赤ちゃんの対応をする体制を整えることが、この大変な時期を乗り切る鍵です。
5. 8ヶ月赤ちゃんの夜泣きが激しいときに試したいこと
これまでよく寝ていたのに、8ヶ月頃になって急に夜泣きが激しくなることがあります。これは「8ヶ月の壁」とも呼ばれ、赤ちゃんの成長過程で多くの親子が経験するものです。
5-1. 8ヶ月赤ちゃんの夜泣きが起こる原因とは?
- 分離不安や人見知りが始まる時期
- ママやパパなど、特定の養育者との愛着が深まり、知らない人や場所に対して不安を感じる「人見知り」が始まります。同時に、ママの姿が見えないと不安になる「分離不安」も強くなるため、夜中に目を覚ましやすくなります。
- 昼間の刺激が多すぎて睡眠に影響する場合
- ずりばいやハイハイが始まり行動範囲が広がることで、日中に受ける刺激が格段に増えます。楽しかった出来事や新しい体験が脳を興奮させ、夜になってもなかなか寝付けなかったり、夜泣きに繋がったりします。
5-2. 効果的な対応法と親が気をつけるポイント
8ヶ月の夜泣きは成長の証です。焦らず、赤ちゃんの心に寄り添う対応を心がけましょう。
- 優しく抱っこして安心感を与える
不安で泣いている赤ちゃんには、抱っこや優しい声かけが一番の薬です。「大丈夫だよ」と伝えて、安心させてあげましょう。 - 強く叱ったり無視しないよう注意する
泣き声にイライラしてしまう気持ちも分かりますが、叱ったり放置したりすると、赤ちゃんの不安を煽って逆効果になることがあります。
6. 7ヶ月赤ちゃんが急に夜泣きを始めたらどうする?
生後7ヶ月頃は、お座りが安定したり、寝返りが上手になったりと、運動機能が大きく発達する時期です。体の成長と睡眠パターンの変化が、夜泣きの原因となることがあります。
6-1. 7ヶ月赤ちゃんと睡眠パターンの変化について
- 睡眠サイクルが変化し浅い眠りになることが増える
- 赤ちゃんの睡眠は、少しずつ大人のパターンに近づいていきます。その過程で、レム睡眠(浅い眠り)の割合が増え、ちょっとした刺激で目を覚ましやすくなることがあります。
- 新しい刺激への反応によって目覚めやすくなる
- 日中にできることが増え、好奇心も旺盛になります。様々な刺激を脳が処理しきれず、夜中に興奮して泣いてしまうことがあります。
6-2. 夜泣きを防ぐための日中活動へのアプローチ
- 日中に適度な遊び時間を設ける
- 体を動かす遊びと、絵本を読むなどの静かな遊びをバランスよく取り入れましょう。日中に心地よい疲労感を感じることで、夜ぐっすり眠りやすくなります。
- 刺激量を調整して過剰にならないよう心掛ける
- 特に寝る前は、激しい遊びやテレビの視聴は避け、静かでリラックスできる環境を整えてあげることが大切です。
7. 9ヶ月赤ちゃんと6ヶ月赤ちゃんで異なる夜泣き対策
同じ乳児期でも、発達段階によって夜泣きの原因や適切な対応は異なります。ここでは9ヶ月と6ヶ月の赤ちゃん、それぞれの特徴に合わせた対策をご紹介します。
7-1. 9ヶ月赤ちゃん向け:自立心を育む方法とは?
9ヶ月頃になると、つかまり立ちを始めたり、後追いが激しくなったりと、心身ともに大きな成長を見せます。少しずつ「自分で眠る力」を育むサポートを始めるのに良い時期です。
- 自分で寝付ける習慣を少しずつ促す
- 抱っこで完全に寝かしつけるのではなく、ウトウトし始めたら布団に下ろしてみましょう。最初は泣いてしまうかもしれませんが、背中をトントンしたり、子守唄を歌ったりして、「一人でも眠れるんだ」という自信を少しずつ育てていきます。
- 過度な介入ではなく見守りながら対応する
- 夜中に少しぐずった時に、すぐに抱き上げずに数分様子を見ることも一つの方法です。赤ちゃんが自力で再び眠りにつくチャンスを与えることになります。もちろん、激しく泣き始めたらすぐに安心させてあげましょう。
7-2. 6ヶ月赤ちゃん向け:安心感を高める工夫
寝返りができるようになり、周囲への興味も増してくる6ヶ月頃。この時期の夜泣きには、まずたっぷりの安心感を与えてあげることが何よりも重要です。
- 添い寝や抱っこで安心感を与える時間を増やす
- まだまだママやパパのぬくもりを必要としている時期です。夜泣きをした時には、優しく抱きしめたり、添い寝をして背中をさすってあげたりして、不安を取り除いてあげましょう。
- 親とのコミュニケーション時間を意識的に確保する
- 日中に、絵本を読んだり、歌をうたったり、話しかけたりする時間をたくさん作りましょう。親との愛着関係が深まることで、赤ちゃんの心の安定に繋がり、夜泣きの軽減も期待できます。
理想の保育園・幼稚園探しなら「エンクル」 検索して地図上で空き情報を一括比較!口コミや見学予約機能も。登録した希望条件でオファーも届く!
保育園探しはプロにお任se!希望の園探しをトコトンお手伝いします!
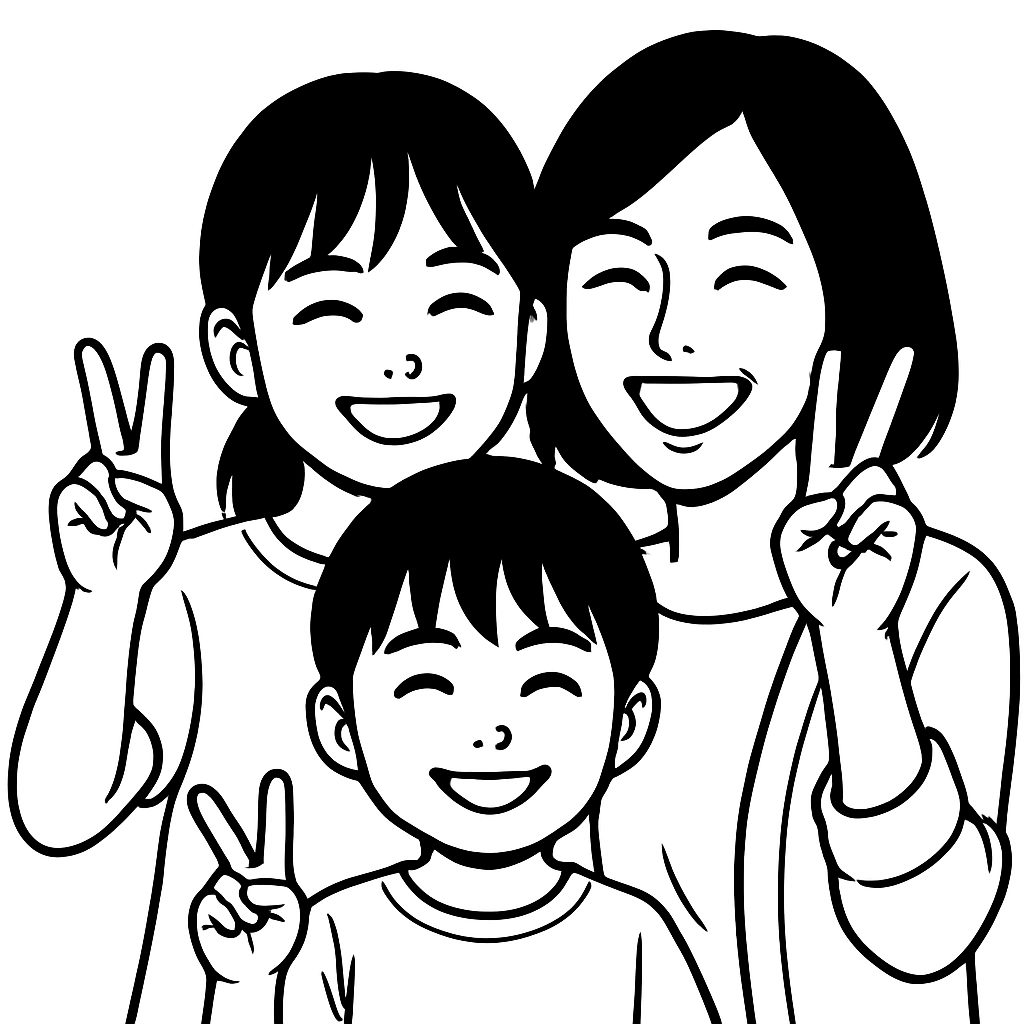
保活アドバイザーのもっちゃんです。小3の娘と年少の息子を育てる2児の母。保育園の転園を経験し、実体験をもとに保活&子育て情報を発信中。癒しは愛猫とのまったり時間です。









