
「周りの子はもうお箸を使っているのに、うちの子はまだ…」「保育園の入園も近いし、そろそろ練習しないとダメかな?」「でも、どうやって教えたらいいの?無理強いして食事嫌いになったらどうしよう…」
2歳、3歳頃になると、子どものお箸の練習について、こんな不安や焦りを感じるパパ・ママは少なくありません。
ご安心ください。お箸の練習で最も大切なのは、お子さんの発達に合わせたタイミングで、親子で楽しく進めることです。
この記事では、
- お箸を始めるべき最適な時期を見極めるサイン
- 遊びながら準備できる指先トレーニング
- イラストで分かる正しい持ち方と教え方の全ステップ
- 失敗しないトレーニング箸の選び方と比較
- 親がイライラしないための3つの心構え
まで、網羅的に解説します。この記事を読ばれば、お箸の練習に関する不安が解消され、自信を持ってお子さんと向き合えるようになります。焦らず、お子さんの「できた!」を一緒に喜びながら、食事の時間をより豊かなものにしていきましょう。
目次
- 1. お箸の練習、こんなことで悩んでいませんか?
- 1-1. 周りの子と比べて焦ってしまう
- 1-2. いつから始めるべきかタイミングがわからない
- 1-3. 正しい持ち方の教え方がわからない
- 1-4. 子どもが嫌がって練習にならない
- 1-5. トレーニング箸は本当に必要なのか迷う
- 2. 結論:お箸の練習は「2歳〜3歳頃」が目安。でも焦らないで!
- 2-1. なぜ2歳〜3歳頃?指先が器用になる時期
- 2-2. 最も大切なのは「本人のやる気」と「発達」
- 2-3. 保育園入園前に完璧にする必要はありません
- 3. お箸を始める前に!家庭でできる「3つの発達チェックリスト」
- 3-1. サイン1:スプーン・フォークを鉛筆のように持てるか
- 3-2. サイン2:大人の真似をしてお箸を使いたがるか
- 3-3. サイン3:指先の器用さチェック(ピースサイン、グーチョキパーができるか)
- 4. いきなり箸はNG!遊びながら指先を鍛える準備運動3選
- 4-1. ①【つまむ力】粘土やブロック遊び
- 4-2. ②【器用さ】シール貼りやお絵描き
- 4-3. ③【はさむ感覚】トングを使ったおままごと
- 5. 【イラストで完全解説】正しいお箸の持ち方と教え方の4ステップ
- 5-1. STEP0:まずは正しい持ち方を大人が再確認しよう
- 5-2. STEP1:上の箸1本だけを持って動かす練習
- 5-3. STEP2:2本を持って開閉する練習(輪ゴムの裏技も紹介)
- 5-4. STEP3:ゲーム感覚で!掴みやすいもので実践練習
- 5-5. STEP4:食事で使ってみよう(最初の5分だけでもOK)
- 6. トレーニング箸は必要?メリット・デメリットと選び方【おすすめ3選】
- 6-1. トレーニング箸のメリットと注意点
- 6-2. 【比較表】トレーニング箸の種類と特徴(連結・リング・くぼみ)
- 6-3. トレーニング箸から普通の箸へ移行するタイミングは?
- 7. 親子バトル回避!パパ・ママがイライラしないための3つの心構え
- 7-1. ①叱らない・強制しない(食事の時間を楽しいものに)
- 7-2. ②できたら大げさに褒める(具体的な声かけ例)
- 7-3. ③他人と比べない(比べる相手は昨日のわが子)
- 8. 【将来のために】食事中に教えたいお箸の基本マナー
- 8-1. やってはいけない「嫌い箸(忌み箸)」とは?
- 8-2. 正しいお箸の置き方
- 9. 【保活中の方向け】保育園ではお箸の練習をどうしてる?
- 9-1. 保育園で箸の練習が始まるのはいつから?
- 9-2. 保育士はここを見ている!専門的なアプローチとは
- 9-3. 園見学で確認したい!食事に関する質問リスト
- 10. お箸の練習に関するQ&A
- 10-1. Q. 左利きの場合はどう教えればいいですか?
- 10-2. Q. 何度教えても変な持ち方の癖が直りません。どうすればいいですか?
- 10-3. Q. おすすめの練習用おもちゃはありますか?
- 11. まとめ:焦らず楽しく、正しい箸の持ち方をマスターしよう
1. お箸の練習、こんなことで悩んでいませんか?
子どものお箸の練習を考え始めると、次から次へと悩みや疑問が浮かんできますよね。多くのパパ・ママが、同じようなことで悩んでいます。
1-1. 周りの子と比べて焦ってしまう
同じ月齢の子がお箸を上手に使っているのを見ると、「うちの子は遅れているのかも…」とつい焦ってしまいます。子どもの成長は一人ひとり違うと頭では分かっていても、不安になるのは自然なことです。
1-2. いつから始めるべきかタイミングがわからない
「早すぎても良くないって聞くし、遅すぎると癖がつくとも言うし…」。お箸の練習を始めるべき最適なタイミングが分からず、一歩を踏み出せないという声もよく聞きます。
1-3. 正しい持ち方の教え方がわからない
自分自身が何気なく使っているお箸だからこそ、いざ子どもに教えるとなると「どうやって説明したらいいの?」と戸惑ってしまいます。言葉で説明してもなかなか伝わらず、悩んでしまう方も多いでしょう。
1-4. 子どもが嫌がって練習にならない
いざ練習を始めても、子どもが全く興味を示さなかったり、すぐに「やりたくない!」と嫌がったりすることも。無理強いして食事そのものが嫌いになってしまったら…と心配になりますよね。
1-5. トレーニング箸は本当に必要なのか迷う
様々な種類のトレーニング箸が売られていますが、「本当に効果があるの?」「どれを選べばいいかわからない」「なくても練習できるのでは?」と、購入を迷っている方も少なくありません。
2. 結論:お箸の練習は「2歳〜3歳頃」が目安。でも焦らないで!
お箸の練習を始める時期について、結論からお伝えすると、一般的には2歳〜3歳頃が目安とされています。しかし、これはあくまで目安であり、すべての子どもに当てはまるわけではありません。
2-1. なぜ2歳〜3歳頃?指先が器用になる時期
この時期になると、多くの子どもは脳や身体の発達が進み、指先を自分の思い通りに動かせるようになってきます。スプーンやフォークを上手に使えるようになったり、クレヨンで線を描けるようになったりと、お箸を使うための基礎的な能力が育ってくるのです。
2-2. 最も大切なのは「本人のやる気」と「発達」
月齢や年齢以上に大切なのが、お子さん本人の「お箸を使いたい!」という気持ちと、指先の発達具合です。大人の真似をしたがったり、お箸に興味を示したりといったサインが見られたら、それは絶好の始めどきかもしれません。逆に、まだ興味がないのに無理やり始めると、お箸や食事に対してネガティブなイメージを持ってしまう可能性もあります。
2-3. 保育園入園前に完璧にする必要はありません
「保育園に入るまでにお箸を使えるようにしないと!」と焦る必要は全くありません。
多くの保育園では、子どもの発達に合わせてスプーンやフォークを併用しながら、ゆっくりとお箸の練習を進めていきます。入園前に完璧を目指すのではなく、まずは「お箸って楽しいな」と思える経験をさせてあげることが大切です。
3. お箸を始める前に!家庭でできる「3つの発達チェックリスト」
お箸の練習を始める前に、お子さんがお箸を使える準備ができているか、いくつかのサインで確認してみましょう。
以下の3つのポイントがクリアできていれば、スムーズに練習を始められる可能性が高いです。
3-1. サイン1:スプーン・フォークを鉛筆のように持てるか
スプーンやフォークを下から握る「グー持ち」ではなく、上から鉛筆のように持てる(三指持ち)ようになっているかは重要なポイントです。これは、お箸を操作する指の動きの基礎となります。食事の際に、持ち方をさりげなくチェックしてみてください。
3-2. サイン2:大人の真似をしてお箸を使いたがるか
パパやママが使っているお箸に興味を示し、「自分も使ってみたい!」という素振りを見せるのは、意欲が芽生えている証拠です。子どもの「やってみたい」という気持ちは、何よりの原動力になります。このサインを見逃さず、タイミングを合わせてあげましょう。
3-3. サイン3:指先の器用さチェック(ピースサイン、グーチョキパーができるか)
お箸は、親指・人差し指・中指の3本を複雑に動かして使います。
- ピースサイン(チョキ)ができるか
- 親指と人差し指でOKサインが作れるか
- ジャンケンのグー・チョキ・パーがスムーズにできるか
これらの動きができるということは、指を一本一本独立させて動かす能力が育っている証拠です。遊びの中で、ぜひ試してみてください。
4. いきなり箸はNG!遊びながら指先を鍛える準備運動3選
お箸を上手に使うためには、指先の細かな動きや力加減が不可欠です。いきなりお箸を持たせるのではなく、まずは楽しい遊びを通して、必要な力を自然に養っていきましょう。
4-1. ①【つまむ力】粘土やブロック遊び
粘土を指先でちぎったり、丸めたり、こねたりする遊びは、指先の筋肉を鍛えるのに最適です。また、小さなブロックを指でつまんで組み立てる遊びも、「つまむ」というお箸の基本動作に繋がります。
4-2. ②【器用さ】シール貼りやお絵描き
細かいシールを台紙から剥がして、狙った場所に貼る作業は、指先の集中力と器用さを高めます。クレヨンや色鉛筆で線や円を描くお絵描きも、手首や指をコントロールする良い練習になります。
4-3. ③【はさむ感覚】トングを使ったおままごと
おままごとで使うおもちゃのトングは、お箸で「はさむ」感覚を疑似体験できる優れたアイテムです。ポンポンやスポンジなど、軽くて掴みやすいものを、お皿からお皿へ移す遊びを取り入れてみましょう。「上手だね!」と褒めてあげることで、子どものやる気もアップします。
5. 【イラストで完全解説】正しいお箸の持ち方と教え方の4ステップ
準備が整ったら、いよいよお箸の持ち方を教えていきましょう。焦らず、一つひとつのステップをクリアしていくことが成功の鍵です。
5-1. STEP0:まずは正しい持ち方を大人が再確認しよう
子どもに教える前に、まずはパパ・ママ自身が正しい持ち方をおさらいしておくことが大切です。
- 下の箸:薬指と親指の付け根で固定
- 下の箸は動かしません。薬指の爪の横あたりに乗せ、親指と人差し指の付け根部分でしっかりと挟んで固定します。

- 上の箸:鉛筆持ちで3本の指で動かす
- 上の箸は、鉛筆を持つときのように親指・人差し指・中指の3本で軽く持ちます。実際に動かすのはこの上の箸だけです。

- よくある間違った持ち方(にぎり箸・クロス箸)
- 最初に間違った持ち方が癖になってしまうと、後から直すのが大変です。にぎるように持つ「にぎり箸」や、箸が途中で交差してしまう「クロス箸」になっていないか、注意して見てあげましょう。
5-2. STEP1:上の箸1本だけを持って動かす練習
まずは、動かす方の上の箸だけを鉛筆持ちで持たせます。そして、人差し指と中指を曲げたり伸ばしたりして、箸先を上下に動かす練習をしてみましょう。「こんにちは、とお辞儀させてみようか」など、遊び感覚で声をかけると楽しんでくれます。
5-3. STEP2:2本を持って開閉する練習(輪ゴムの裏技も紹介)
STEP1の動きに慣れたら、下の箸をそっと添えて2本持ちに挑戦します。最初はうまく開閉できなくても大丈夫です。
【裏技】
親指に輪ゴムをかけ、2本の箸を八の字になるように通すと、自然とお箸が開くのをサポートしてくれます。この状態でカチカチと箸先を合わせる練習を繰り返しましょう。
5-4. STEP3:ゲーム感覚で!掴みやすいもので実践練習
お箸の開閉ができるようになったら、いよいよ物を掴む練習です。食事でいきなり使うのではなく、まずはゲーム感覚で楽しめるものから始めましょう。
- 角切りにしたスポンジ
- 丸めたティッシュペーパー
- ボーロなどのお菓子
お皿からお皿へ移す競争をするなど、親子で楽しみながら挑戦するのがおすすめです。
5-5. STEP4:食事で使ってみよう(最初の5分だけでもOK)
練習で上手に掴めるようになったら、食事の際に使ってみましょう。ただし、最初からすべてをお箸で食べさせようとする必要はありません。子どもはまだ上手に使えないため、時間がかかってお腹が空いてしまいます。「最初の5分だけ挑戦してみようか」などと時間を区切り、残りはスプーンやフォークを使っても良いことにしましょう。成功体験を少しずつ積み重ねることが大切です。
6. トレーニング箸は必要?メリット・デメリットと選び方【おすすめ3選】
お箸の練習の心強い味方である「トレーニング箸」。使うべきか迷う方も多いですが、メリットと注意点を理解して上手に活用するのがおすすめです。
6-1. トレーニング箸のメリットと注意点
- メリット
-
- 指を置く位置が分かりやすく、自然と正しいフォームが身につく
- 連結されているものが多く、箸がばらけず操作しやすい
- 子どもが好きなキャラクターものなどもあり、練習への意欲が高まる
- 注意点
-
- トレーニング箸の形に慣れすぎると、普通の箸への移行でつまずくことがある
- 種類によっては洗浄がしにくいものもある
トレーニング箸はあくまで「正しい指の動きを覚えるための補助器具」と捉え、ある程度慣れてきたら普通の箸に移行していく意識を持つことが大切です。
6-2. 【比較表】トレーニング箸の種類と特徴(連結・リング・くぼみ)
トレーニング箸は、大きく分けて3つのタイプがあります。お子さんの発達段階に合わせて選びましょう。
| 種類 | 特徴 | こんな子におすすめ |
|---|---|---|
| 連結タイプ | 箸の上部が連結されており、バネの力で開くのを補助してくれる。 | ・お箸デビューの初心者 ・まだ指の力が弱い子 |
| リングタイプ | 指を入れるリングが付いており、正しい指の位置を覚えられる。 | ・持ち方が安定しない子 ・自己流の癖がつき始めている子 |
| くぼみタイプ | 指を置く場所にくぼみや印が付いているシンプルな形状。 | ・トレーニング箸からの卒業を目指す子 ・普通の箸に近い感覚で練習したい子 |
6-3. トレーニング箸から普通の箸へ移行するタイミングは?
トレーニング箸で上手に食べられるようになり、食事中に補助なしで箸を操作できる時間が増えてきたら、移行を検討するタイミングです。
連結タイプ→リングタイプ→くぼみタイプ→普通の箸、というように段階を踏むとスムーズです。最初は食事の後半だけ普通の箸にしてみるなど、少しずつ慣らしていきましょう。
7. 親子バトル回避!パパ・ママがイライラしないための3つの心構え
お箸の練習がうまくいかないと、ついイライラしてしまいがちです。しかし、親の焦りは子どもに伝わり、練習が嫌いになる原因にもなりかねません。
親子で楽しく乗り越えるために、以下の3つのことを心に留めておきましょう。
7-1. ①叱らない・強制しない(食事の時間を楽しいものに)
「持ち方が違うでしょ!」「なんでできないの!」といった叱責は絶対にNGです。
子どもは萎縮してしまい、お箸を使うこと自体が苦痛になってしまいます。できなくても当たり前。食事は楽しい時間であるということを、何よりも優先してください。
7-2. ②できたら大げさに褒める(具体的な声かけ例)
どんなに小さなことでも、できたら「すごい!」「上手につまめたね!」と、少し大げさなくらい褒めてあげましょう。
子どもの達成感と自己肯定感を育むことが、次へのモチベーションに繋がります。
- 「うわー!お豆さん、お箸でお引越しできたね!」
- 「人差し指が上手に動いてるね、かっこいい!」
- 「昨日より上手になったんじゃない?」
7-3. ③他人と比べない(比べる相手は昨日のわが子)
子どもの成長スピードは、本当に人それぞれです。
「あの子はもうできているのに」と他人と比べるのはやめましょう。比べるべき相手は、「昨日のわが子」です。昨日できなかったことが今日少しでもできるようになったら、その小さな進歩を一緒に喜んであげてください。
8. 【将来のために】食事中に教えたいお箸の基本マナー
お箸が上手に使えるようになったら、少しずつ食事のマナーについても教えていきましょう。将来、子どもが恥ずかしい思いをしないための大切な教えです。
8-1. やってはいけない「嫌い箸(忌み箸)」とは?
日本では、お箸の使い方には様々なタブーがあります。代表的なものをいくつかご紹介します。
- 刺し箸
料理にお箸を突き刺して食べること。 - 迷い箸
どのおかずを食べようか、お皿の上でお箸を動かし迷うこと。 - 寄せ箸
お箸で食器を引き寄せること。 - 渡し箸
お箸を食器の上に橋のように置くこと。
これらを一度にすべて教える必要はありません。食事中に見かけたら、「お箸でお皿を動かすのはお休みしようね」などと、その都度優しく伝えていきましょう。
8-2. 正しいお箸の置き方
お箸を使わないときは、箸置きに箸先をそろえて置くのが基本です。箸置きがない場合は、お皿の縁に箸先をかけて置きます。お茶碗の上などに「渡し箸」をしないように教えてあげましょう。
9. 【保活中の方向け】保育園ではお箸の練習をどうしてる?
2歳児クラスからの入園を考えている方にとって、保育園での食事指導の方針は気になるところですよね。
9-1. 保育園で箸の練習が始まるのはいつから?
多くの保育園では、2歳児クラス(3歳になる年)あたりから、子どもの発達状況を見ながら少しずつお箸の練習を始めます。ただし、園の方針や子ども一人ひとりのペースを尊重するため、一斉にスタートするわけではありません。最初はスプーンやフォークと併用し、無理なく進めていくのが一般的です。
9-2. 保育士はここを見ている!専門的なアプローチとは
保育士は、単に「お箸が使えるか」だけを見ているわけではありません。
- 指先の発達は十分か
- 食事に意欲的に取り組んでいるか
- 道具(スプーン・フォーク)を正しく使えているか
- 自分で食べようとする気持ちがあるか
これらの点を総合的に判断し、その子に合ったタイミングで声かけをしたり、持ち方を援助したりします。家庭と連携を取りながら、子どものペースを大切に進めてくれるので安心してください。
9-3. 園見学で確認したい!食事に関する質問リスト
保育園見学は、園の食事に関する方針を知る絶好の機会です。ぜひ、以下のような質問をしてみてください。
- お箸の練習はいつ頃から、どのように進めていますか?
- 食事の際に、子ども一人ひとりのペースに合わせて援助してもらえますか?
- アレルギー対応はどのようにしていますか?
- 食育活動(野菜の栽培など)は行っていますか?
- 食事のマナーについては、どのように教えていますか?
これらの質問を通して、園がどれだけ子どもの「食」を大切に考えているかを知ることができます。
10. お箸の練習に関するQ&A
10-1. Q. 左利きの場合はどう教えればいいですか?
A. 基本的な教え方は右利きの場合と同じです。無理に右利きに矯正する必要はありません。パパやママが右利きの場合、対面で座って鏡のように動きを見せてあげると、子どもは真似しやすくなります。左利き用のお箸も市販されているので、活用するのも良いでしょう。
10-2. Q. 何度教えても変な持ち方の癖が直りません。どうすればいいですか?
A. 一度ついた癖を直すのは根気が必要です。焦らず、まずは「STEP1:上の箸1本だけを持って動かす練習」に戻ってみましょう。正しい指の動きを再確認することが大切です。また、食事以外の時間に、お箸を使ったゲームなどで楽しく練習する機会を増やすのも効果的です。どうしても直らない場合は、一度お箸から離れて、指先を使う遊びをたくさん取り入れる期間を設けるのも一つの方法です。
10-3. Q. おすすめの練習用おもちゃはありますか?
A. 「マナー豆」や「お豆つかみゲーム」といった、お箸で豆などの小さなアイテムを掴むおもちゃが人気です。これらはゲーム性が高く、楽しみながら集中力と指先の器用さを養うことができます。年齢に合わせて難易度が選べるものもあるので、お子さんに合ったものを選んであげてください。
11. まとめ:焦らず楽しく、正しい箸の持ち方をマスターしよう
今回は、子どものお箸の練習について、始める時期から具体的な教え方、親の心構えまで詳しく解説しました。
- 始める時期
2歳〜3歳頃が目安だが、本人のやる気と発達が最も重要。 - 始める前の準備
「スプーンの持ち方」「本人の興味」「指先の器用さ」をチェック。 - 教え方のステップ
①上の箸1本→②2本で開閉→③ゲームで練習→④食事で実践、と段階を踏む。 - トレーニング箸
メリットを理解し、子どもの発達に合ったものを選んで上手に活用する。 - 親の心構え
叱らない、褒める、比べないの3つを大切に、食事の時間を楽しいものにする。
お箸の練習は、子どもの成長における大切なステップですが、焦りは禁物です。一番大切なのは、お子さんが「自分で食べられた!」という達成感を味わい、食事の時間を楽しむことです。この記事を参考に、ぜひお子さんのペースに合わせて、親子で楽しくお箸の練習に取り組んでみてください。
保育園での食事指導の方針も、園見学でしっかり確認しよう!
「うちの子に合った食事指導をしてくれる保育園はどこだろう?」
「園見学で何を聞けばいいか、もっと知りたい!」
そんな保活中のパパ・ママには、保育施設検索サイト「エンクル」がおすすめです。お住まいの地域やこだわりの条件で、たくさんの保育施設を簡単に検索・比較できます。
気になる園が見つかったら、サイトから園見学の予約も可能です。見学の際には、この記事で紹介した「食事に関する質問リスト」を参考に、園の方針をしっかり確認してみてくださいね。あなたとお子さんにぴったりの保育園がきっと見つかります。
理想の保育園・幼稚園探しなら「エンクル」 検索して地図上で空き情報を一括比較!口コミや見学予約機能も。登録した希望条件でオファーも届く!
保育園探しはプロにお任せ!希望の園探しをトコトンお手伝いします!
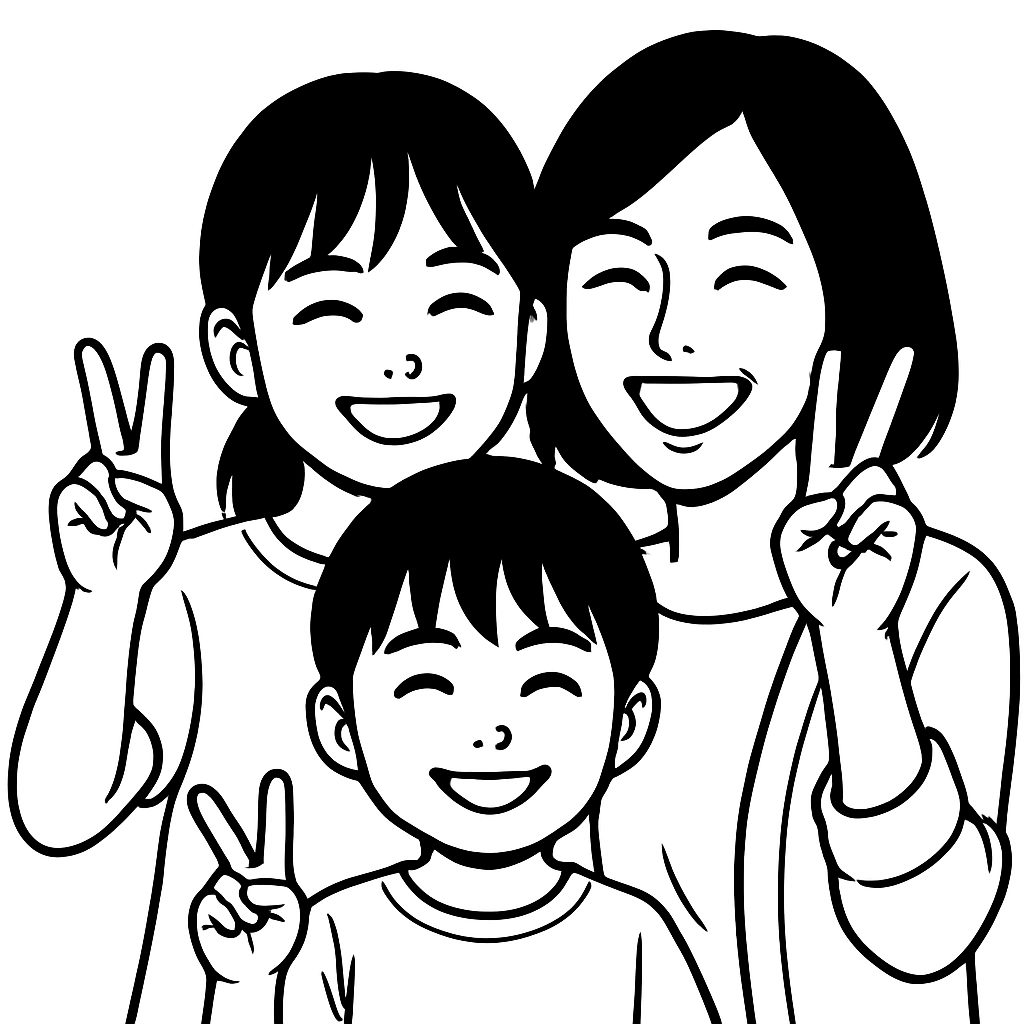
保活アドバイザーのもっちゃんです。小3の娘と年少の息子を育てる2児の母。保育園の転園を経験し、実体験をもとに保活&子育て情報を発信中。癒しは愛猫とのまったり時間です。









