
仕事復帰を控え、いよいよ始まる保育園生活。期待とともに、「子どもが熱を出したらどうしよう」「どのくらいの症状で休ませるべき?」といった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に初めての集団生活では、子どもは様々なウイルスや細菌に触れる機会が増え、体調を崩しやすくなります。
いざという時に慌てないために、そして安心して仕事と育児を両立させるために、保育園を休ませる症状の目安や判断のポイントを知っておくことが大切です。この記事では、熱、鼻水、咳、下痢といった症状別に、登園の基準や家庭でのケアについて詳しく解説します。
目次
1. 保育園に預ける際の熱の基準とは?微熱や発熱の場合の判断ポイント
子どもの体調不良で最も分かりやすいサインが「発熱」です。しかし、「微熱って何度から?」「朝には熱が下がったけど、登園させていいの?」など、判断に迷う場面も多いでしょう。ここでは、熱に関する基準と考え方を見ていきましょう。
1-1. 微熱は何度から?保育園での基準を知る
一般的に、子どもの体温が37.5℃以上になると「発熱」と判断され、保育園をお休みする目安となります。多くの保育園では、登園時の検温で37.5℃以上ある場合や、保育時間中に37.5℃を超えた場合にお迎えの連絡が入ります。
ただし、この基準は園によって異なる場合があるため、入園のしおりや契約書で必ず確認しておきましょう。
知っておきたいポイント
- 平熱の把握
- 子どもは大人より体温が高めです。元気な時に何度か検温し、お子さんの平熱を知っておくと、いざという時の判断材料になります。
- 体温以外の様子
- 熱の数字だけでなく、「食欲がない」「機嫌が悪い」「ぐったりしている」など、普段と違う様子がないかもしっかり観察することが重要です。
1-2. 発熱後はいつから登園OK?前日の夜に熱があった場合の注意
夜に熱があっても、翌朝には解熱していることはよくあります。しかし、すぐに登園させるのは少し待ってください。多くの自治体や保育園では、「解熱後24時間以上が経過し、普段通りに食欲があり元気に過ごせること」を再登園の目安としています。
「仕事があるから」と解熱剤で一時的に熱を下げて登園させるのは、子どもの身体に大きな負担をかけるだけでなく、集団生活の場で感染を広げてしまう可能性もあります。熱がぶり返すことも多いため、朝に平熱でも、念のためその日は自宅で様子を見るのが賢明です。
1-3. 熱が出た後の家でのケアと翌日の保育園対応
熱が出た時は、まずお子さんをゆっくり休ませてあげることが第一です。
家庭でのケア
- 水分補給
- 汗をかくため、脱水症状にならないよう、こまめに水分(湯冷まし、麦茶、幼児用イオン飲料など)を摂らせましょう。
- 衣服の調整
- 熱が上がりきって寒がっている時は暖かく、熱が上がりきって暑がっている時は汗を吸いやすい薄着にするなど、快適に過ごせるよう調整します。
- 食事
- 食欲がなければ無理に食べさせず、消化の良いもの(おかゆ、うどん、すりおろしリンゴなど)を欲しがる時に与えましょう。
翌日登園する際は、朝の受け入れ時に先生へ「昨日の夜に熱がありましたが、今朝は解熱して元気です」といった経緯を正確に伝えることが大切です。
2. 鼻水や咳は休むべき?保育園での判断基準とマナー
熱はないけれど、鼻水や咳が出ている…これもまた判断に迷う症状です。他の園児への配慮も考えながら、どう対応すべきか見ていきましょう。
2-1. 鼻水だけなら大丈夫?保育園に預ける際の注意点
鼻水だけで、熱もなく元気にしている場合は登園できることがほとんどです。しかし、以下の点には注意しましょう。
| チェック項目 | 登園を検討する目安 | 休ませることを検討する目安 |
|---|---|---|
| 鼻水の状態 | 透明でサラサラしている | 黄色や緑色で粘り気がある |
| 量 | 時々出る程度 | 常に垂れている、鼻が詰まって苦しそう |
| 他の症状 | なし | 熱、ひどい咳、目の充血などを伴う |
| 機嫌・食欲 | 普段と変わらない | 不機嫌、食欲がない |
鼻水が出ている状態で登園させる場合は、こまめに鼻をかむ、または拭き取るなどのケアをお願いできるよう、先生に朝の時点で伝えておくとスムーズです。
2-2. 咳がひどい場合どうする?保育園での受け入れ条件
咳も鼻水と同様、症状の程度によって判断が分かれます。軽いコンコンという咳程度で元気であれば登園可能なことが多いですが、下記のような場合はお休みを検討しましょう。
- 咳がひどくて夜眠れていない
- 呼吸をするたびに「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音がする
- 咳き込んで顔色が悪くなる、嘔吐してしまう
- 犬が吠えるような「ケンケン」という特徴的な咳が出る
ひどい咳は本人が辛いだけでなく、周りの子を不安にさせたり、感染症のリスクがあったりします。判断に迷う場合は、自己判断せず、かかりつけ医に相談しましょう。
3. 下痢や嘔吐がある場合は?保育園に預ける際の考え方
下痢や嘔吐は、ウイルス性胃腸炎などの感染症の可能性が高く、特に慎重な判断が求められます。
3-1. 下痢でも熱なしなら登園可能?保育園の対応基準
熱がなくても、下痢をしている場合は注意が必要です。判断のポイントは「回数」と「便の状態」です。
- 回数
普段より排便の回数が多いか - 便の状態
水のような便(水様便)か、形のある軟便か
保育園によっては「1日に3回以上の水様便がある場合は登園を控える」など、具体的な基準を設けている場合があります。感染力の強い病気(ノロウイルス、ロタウイルスなど)の可能性も考えられるため、熱がないからと安易に預けるのは避け、まずは園に相談するのが良いでしょう。
3-2. 嘔吐後はいつから登園可能?保育園で確認すべきポイント
嘔吐があった場合は、原則として保育園はお休みです。一度きりであったとしても、感染症のリスクを考慮し、他の園児にうつさないための重要な対応です。
再登園の目安
- 最後に嘔吐してから24時間以上経過している
- 食事が普段通り(またはそれに近く)摂れている
- 下痢などの他の症状がなく、元気に過ごせている
感染性胃腸炎などの診断を受けた場合は、医師の指示に従い、園によっては「登園許可証」の提出が必要になることもあります。
4. 慣らし保育中に体調不良になった場合の対処法
新しい環境への緊張や疲れから、慣らし保育期間中に体調を崩してしまうお子さんは少なくありません。「せっかく慣れてきたのに…」「職場復帰の予定が…」と焦る気持ちはよく分かりますが、これは多くの親子が通る道です。
4-1. 慣らし保育中の発熱対応と今後のスケジュール調整
慣らし保育中に発熱した場合も、基本的な対応は同じです。まずは園に連絡し、お迎えに行きましょう。そして何より、お子さんの回復を最優先に考えてあげてください。
スケジュールについては、焦らずに保育園の先生と相談することが大切です。
「一度お休みして、回復してからまた同じ時間から再開する」「少し時間を短くして再スタートする」など、お子さんの状況に合わせて柔軟に対応してくれるはずです。
4-2. 慣らし保育で初めて体調不良になった時に親が取るべき行動
初めての集団生活での体調不良は、親にとっても試練です。パニックにならず、以下のステップで対応しましょう。
- 子どもの状態を観察する
まずは慌てずに、熱、咳、食欲、機嫌など、子どもの様子を冷静にチェックします。 - 保育園に連絡・相談する
お迎えの要請があったら速やかに対応し、子どもの状態を正直に伝えて今後の対応を相談します。 - かかりつけ医を受診する
必要に応じて病院を受診し、医師の診断を仰ぎます。 - 職場へ連絡する
状況を説明し、お休みが必要な旨を伝えます。慣らし保育が長引く可能性も共有しておくと、その後の調整がスムーズになります。
保育園生活と子どもの体調不良は切っても切れない関係です。最初は戸惑うことも多いかもしれませんが、一つひとつ経験していくことで、親子で乗り越える力がついていきます。困ったときは一人で抱え込まず、保育園の先生や周りの先輩ママ、そしてかかりつけ医など、頼れる存在に相談しながら進んでいきましょう。
理想の保育園・幼稚園探しなら「エンクル」 検索して地図上で空き情報を一括比較!口コミや見学予約機能も。登録した希望条件でオファーも届く!
保育園探しはプロにお任せ!希望の園探しをトコトンお手伝いします!
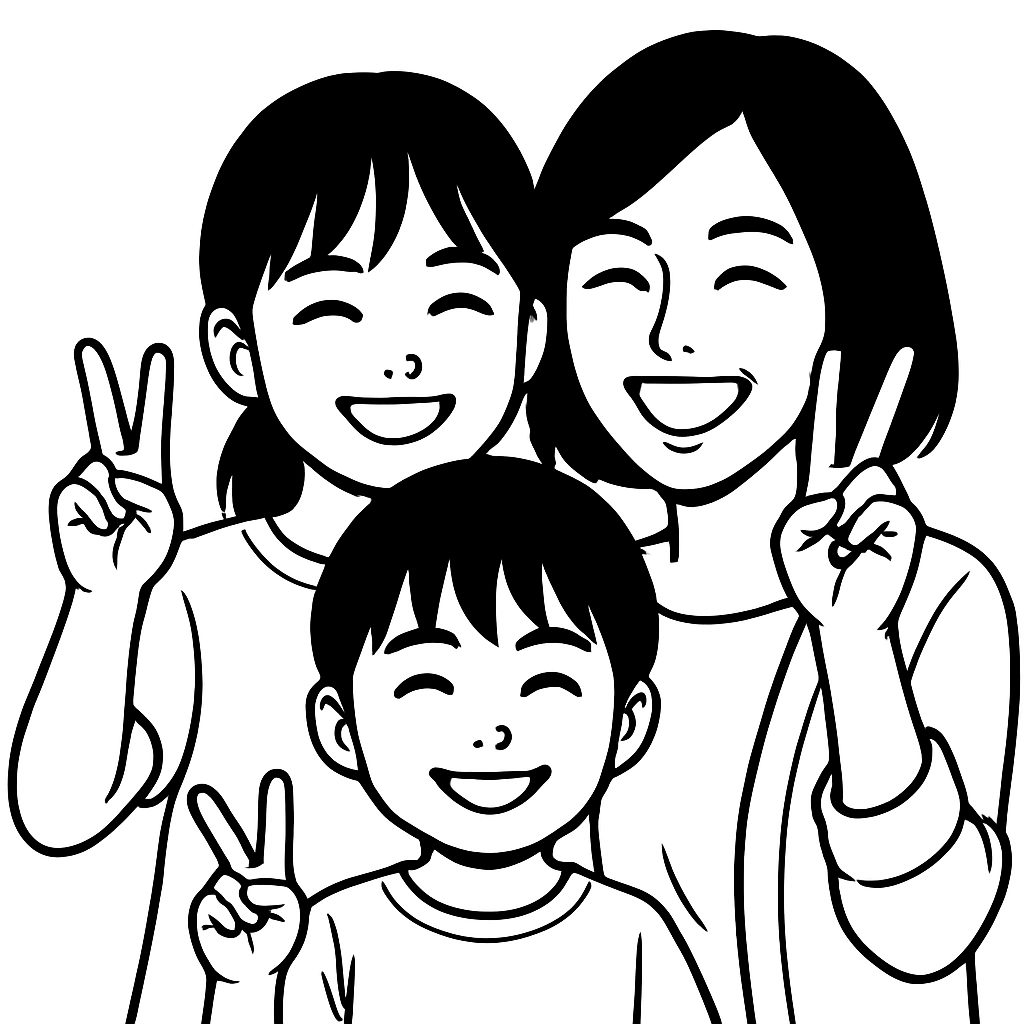
保活アドバイザーのもっちゃんです。小3の娘と年少の息子を育てる2児の母。保育園の転園を経験し、実体験をもとに保活&子育て情報を発信中。癒しは愛猫とのまったり時間です。









