
赤ちゃんの「夜泣き」が続くと、心も体も休まらないと感じますよね。特に、職場復帰を考え保育園を探し始める時期には、日中の活動と夜の対応で、ご自身の時間がなくなりがちです。
この記事では、多くのご家庭が経験する赤ちゃんの夜泣きについて、その時期や原因、そしてご家族で乗り越えるためのヒントをご紹介します。
目次
- 1. 夜泣きはいつから始まるの?赤ちゃんの成長と睡眠の関係
- 2. 夜泣きはいつまで続く?ピークと終わりの目安
- 3. 夜泣きの原因を探る:子どもが夜中に起きる理由とは
- 4. 赤ちゃんや子どもの夜泣きを乗り越えるために親ができること
1. 夜泣きはいつから始まるの?赤ちゃんの成長と睡眠の関係
赤ちゃんの夜泣きは、成長の証でもあります。月齢ごとの睡眠の特徴を知ることで、少しだけ心に余裕が生まれるかもしれません。
1-1. 生後0~3か月の赤ちゃんの睡眠と夜泣き
この時期の赤ちゃんは、まだ昼と夜の区別がついていません。睡眠サイクルも短く、2~3時間おきに目を覚まします。これはお腹が空いたり、おむつが濡れて気持ち悪かったりといった、生理的な欲求が主な原因です。泣いてお知らせしてくれるのは、赤ちゃんが生きるための自然な姿なので、まずはその欲求に応えてあげましょう。
1-2. 生後4~6か月ごろに増える夜泣きの理由
生後4か月を過ぎると、少しずつ昼夜の区別がつき始め、まとまって眠るようになります。しかし、その一方で「睡眠退行」と呼ばれる、一時的に夜中に何度も起きるようになる現象が見られることも。
寝返りを覚えたり、周りの人や物への興味が強まったりと、心と体が大きく成長するこの時期は、日中に受けたさまざまな刺激を脳が処理しきれず、夜泣きに繋がることがあります。
2. 夜泣きはいつまで続く?ピークと終わりの目安
「この夜泣きは、一体いつまで続くのだろう…」と不安に思う方も多いでしょう。夜泣きのピークと終わりの目安について見ていきましょう。
2-1. 夜泣きのピークはいつ?多くの親が経験する時期
一般的に、夜泣きのピークは生後6~10か月ごろに訪れることが多いと言われています。
この時期は、ハイハイやつかまり立ちが始まって行動範囲が広がり、日中の活動がより活発になります。また、人見知りや後追いが始まる時期とも重なり、ママやパパがそばにいない不安から、夜中に目を覚まして泣いてしまうこともあります。
2-2. 子どもの夜泣きが落ち着くタイミングとは
多くの赤ちゃんの夜泣きは、1歳半から2歳ごろには自然と落ち着く傾向があります。
言葉で自分の気持ちを少しずつ伝えられるようになったり、体内時計が整って生活リズムが安定したりすることで、朝までぐっすり眠れる日が増えていきます。保育園などで日中の活動が充実し、生活リズムが整うことも、夜の安眠に繋がる一つの要因です。
3. 夜泣きの原因を探る:子どもが夜中に起きる理由とは
夜泣きの原因は一つではなく、様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられています。考えられる主な原因を整理してみましょう。
- 睡眠サイクルの未熟さ
- 赤ちゃんは大人と比べて眠りが浅い「レム睡眠」の割合が多く、ちょっとした物音や刺激で目を覚ましやすい状態です。
- 日中の刺激
- 楽しかったこと、驚いたこと、怖かったことなど、日中に経験した出来事が刺激となり、夜中に興奮して目覚めてしまうことがあります。
- 生活リズムの乱れ
- 起きる時間や寝る時間、お昼寝のタイミングが日によってバラバラだと、体内時計が乱れて夜の睡眠に影響が出やすくなります。
- 身体的な不快感
- 空腹、のどの渇き、おむつの不快感、暑い・寒いといった室温、衣服の締め付けなど、身体的な不快感が原因で泣いてしまうこともあります。
- 分離不安
- 特に後追いが始まる時期には、眠りから覚めた時にママやパパがいないことに気づき、不安で泣いてしまうことがあります。
- 体調不良
- 鼻づまり、咳、発熱、歯が生え始める際のむずがゆさ(歯ぐずり)など、体調がすぐれないために夜中に起きてしまう場合もあります。

4. 赤ちゃんや子どもの夜泣きを乗り越えるために親ができること
夜泣きはいつか終わると分かっていても、毎日のこととなると本当につらいものです。ここでは、ご家庭で試せる対策をいくつかご紹介します。
4-1. 夜泣きを減らすための生活リズムの整え方
夜にぐっすり眠るためには、日中の過ごし方がとても重要です。
- 朝は同じ時間に起こす
朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、生活リズムが整いやすくなります。 - 日中は適度に体を動かす
天気の良い日はお散歩に出かけたり、室内で安全に遊べるスペースを作ったりして、エネルギーを発散させてあげましょう。 - お昼寝の時間を調整する
夕方以降に長く寝てしまうと夜の睡眠に響くことがあります。月齢に合ったお昼寝の時間を心がけましょう。
保育園を探す際には、園での1日の過ごし方やお昼寝の環境、遊びのプログラムなどを確認しておくと、入園後の生活がイメージしやすくなりますね。
4-2. 夜泣き対策として効果的な環境作り
赤ちゃんが安心して眠れる環境を整えてあげることも大切です。
- 寝る前のルーティンを決める
お風呂に入る、絵本を読む、子守唄を歌うなど、毎日同じ流れで入眠儀式を行うと、赤ちゃんは「これから寝る時間だ」と認識しやすくなります。 - 寝室の環境を整える
部屋を暗くし、静かで快適な温度・湿度を保ちましょう。 - 保護者の方自身がリラックスする
一番大切なのは、保護者の方が心身ともに追い詰められないことです。夜泣き対応は、パートナーと協力・分担し、完璧を目指さないことが大切です。
育児と並行して保育園の情報収集や見学の予約などを進めるのは、時間的にも体力的にも大変なことです。便利なサービスなどを活用してタスクを効率化し、少しでも心と時間に余裕を持つことが、結果としてお子さんとの穏やかな夜に繋がるかもしれません。
理想の保育園・幼稚園探しなら「エンクル」 検索して地図上で空き情報を一括比較!口コミや見学予約機能も。登録した希望条件でオファーも届く!
保育園探しはプロにお任せ!希望の園探しをトコトンお手伝いします!
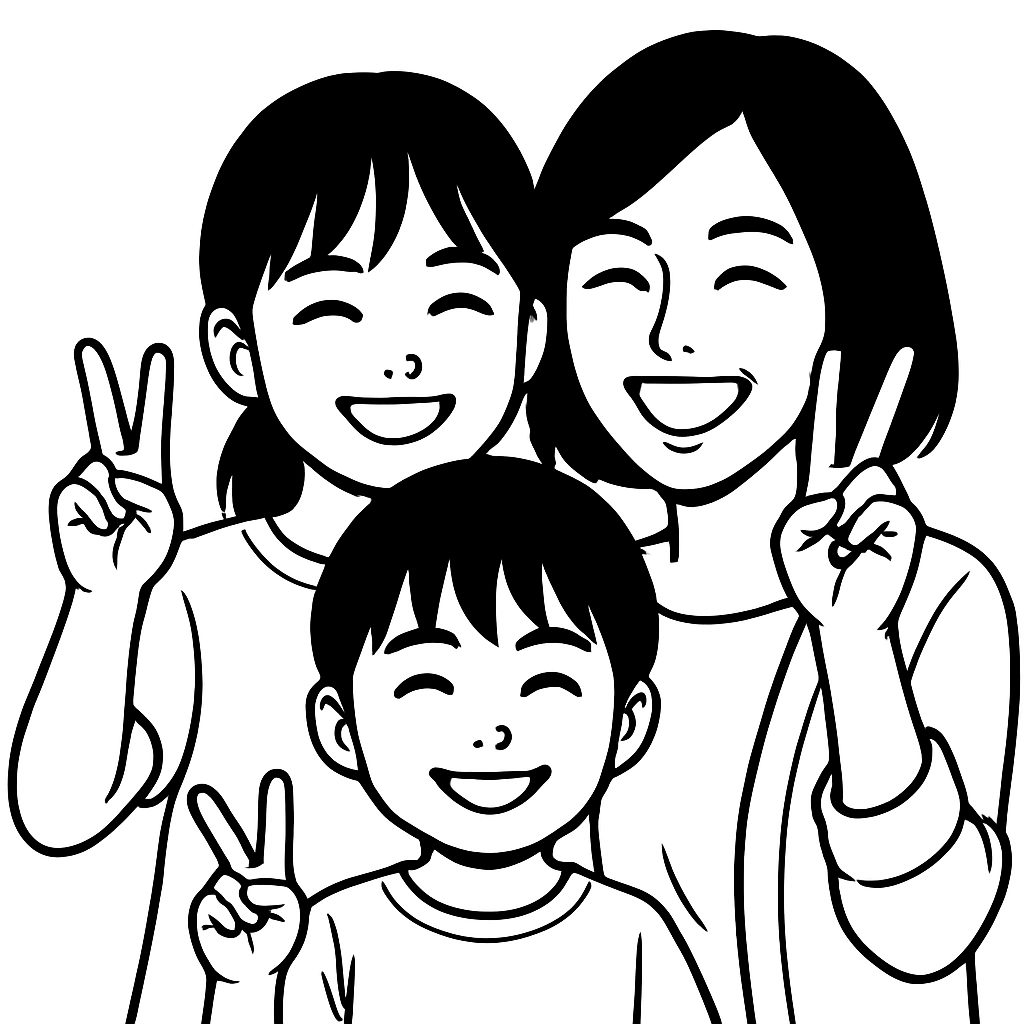
保活アドバイザーのもっちゃんです。小3の娘と年少の息子を育てる2児の母。保育園の転園を経験し、実体験をもとに保活&子育て情報を発信中。癒しは愛猫とのまったり時間です。








