
そろそろ、「保活」という言葉が気になり始める頃ではないでしょうか?「いつから始めればいいの?」「何から手をつければ…」特に「早生まれは不利」なんて話を聞くと、不安になってしまいますよね。初めてのことだらけで、戸惑うのは当然です。
この記事では、そんなプレママ・プレパパの不安を解消するため、保活の基本から具体的なスケジュール、そして妊娠中にこそやっておくべきことまで、網羅的に解説します。保活は情報戦と言われますが、正しい知識と段取りを理解すれば、決して怖いものではありません。
この記事を読めば、保活の全体像がわかり、自信を持って第一歩を踏み出せるようになります。安心して出産準備を進めるためにも、一緒に保活の準備を始めましょう。
目次
- 1. そもそも「保活」とは?今さら聞けない基本を解説
- 2. 保活はいつから始めるべき?全体の流れと年間スケジュール
- 3. 「早生まれ(1〜3月生まれ)は不利」は本当?知っておきたい対策
- 4. 妊娠中にやるべきことリスト!無理なく進める保活5ステップ
- 5. 失敗しない保育園選びの5つのチェックポイント
- 6. 保活に関するよくある質問(Q&A)
1. そもそも「保活」とは?今さら聞けない基本を解説
まずは「保活」の基本からおさらいしましょう。言葉は聞いたことがあっても、具体的な内容はよくわからないという方も多いはずです。
1-1. 保活とは「保育園に入れるための活動」のこと
保活とは、子どもを保育園に入れるために保護者が行う一連の活動のことです。具体的には、情報収集から保育園の見学、入園申し込み、そして内定を得るまでの一連の流れを指します。
1-2. なぜ保活は必要なの?
なぜ、わざわざ「活動」と名前がつくほど、保育園探しが大変なのでしょうか。その背景には、都市部を中心とした待機児童問題があります。希望するすべての家庭が、希望するタイミングで保育園に入れるわけではないのが現状です。
特に、人気のある保育園や駅に近い便利な保育園は定員を上回る申し込みが集まるため、入園するためには計画的な準備と情報収集が不可欠になります。そのため、「保活」という言葉が生まれ、多くの保護者が早期から準備を始めているのです。
1-3. 保育園にはどんな種類がある?認可と認可外の違い
保育園には、国の基準を満たして運営されている「認可保育施設」と、それ以外の「認可外保育施設」があります。それぞれに特徴があるため、違いを理解しておくことが大切です。
| 施設の種類 | 特徴 | 申し込み先 | 保育料 |
|---|---|---|---|
| 認可保育園 | 国の設置基準(広さ、職員数など)をクリアし、都道府県知事等に認可された施設。 | 自治体 | 世帯所得に応じて変動 |
| 認定こども園 | 幼稚園と保育園の両方の機能を持ち合わせている施設。教育・保育を一体的に行う。 | 自治体 | 世帯所得に応じて変動 |
| 小規模保育事業 | 0〜2歳児を対象とした、定員6〜19人の少人数制の保育施設。 | 自治体 | 世帯所得に応じて変動 |
| 認可外保育施設 | 国の認可基準は満たしていないが、自治体独自の基準などで運営される施設。独自の教育方針を持つ園も多い。 | 各施設に直接 | 施設ごとに一律 |
認可保育施設は保育料が比較的安い傾向にありますが、入園の可否は自治体が決定します。一方、認可外保育施設は保育料が高めになることが多いですが、保護者が直接契約するため、比較的入りやすい場合もあります。
1-4. 保育園の入園選考はどう決まる?「点数(指数)」の仕組み
認可保育園の入園選考は、「利用調整」と呼ばれ、保護者の状況を点数化した「指数」の高い世帯から優先的に入園が決まる仕組みになっています。この点数が高いほど、希望の保育園に入りやすくなります。
- 基準指数
- 保護者の就労状況(勤務時間や日数など)や健康状態といった、基本的な保育の必要度を示す点数です。両親がフルタイムで働いている場合が最も高くなるのが一般的です。
- 調整指数
- 世帯の状況に応じて加点または減点される点数です。例えば、兄弟姉妹が同じ園に在園している場合は加点、近くに子どもをみられる祖父母がいる場合は減点といった調整が行われます。
この点数の計算方法は自治体によって異なるため、必ずお住まいの自治体のホームページや窓口で確認しましょう。
2. 保活はいつから始めるべき?全体の流れと年間スケジュール
「保活は早く始めた方がいい」と聞くけれど、具体的にいつから動けば良いのでしょうか。ここでは、一般的なスケジュールと全体の流れを解説します。
2-1. 結論:妊娠中〜生後半年までに始めるのが理想
結論から言うと、保活を始める最適なタイミングは、妊娠中から子どもが生後半年になる頃までです。特に、最も入園しやすいと言われる「0歳児クラスの4月入園」を目指す場合、申し込みは前年の秋頃に始まります。
出産後は育児で忙しくなり、なかなか時間が取れないことも多いため、体調が安定している妊娠中から情報収集を始めておくと、後々の負担が軽くなります。
2-2. 【4月入園を目指す場合】一般的な保活スケジュール
ここでは、最も一般的な「4月入園」を目指す場合のスケジュール例をご紹介します。
- 4月~6月:情報収集の開始
- 自治体のホームページで保育園の情報をチェック
- 自分の家庭の「点数」が何点になるかシミュレーション
- 認可外保育園の情報も集め始める
- 7月~9月:保育園見学
- 気になる保育園をリストアップし、見学の予約を入れる
- 実際に園を訪れ、雰囲気や保育方針を確認する
- 複数の園を見学して比較検討する
- 10月~12月:入園申し込み
- 自治体の窓口で申込書類を受け取り、必要書類を準備する(就労証明書など)
- 希望する保育園の順位を決めて、申し込み手続きを行う
- 1月~2月:内定通知
- 自治体から選考結果が通知される
- 内定した場合は、園での面談や健康診断に進む
- 2月~3月:二次募集・入園準備
- 一次選考で決まらなかった場合、空きのある園の二次募集に申し込む
- 入園が決まったら、必要な物品の準備や名前つけなどを始める
2-3. 年度途中の入園はできる?
4月以外のタイミングで入園(年度途中入園)することも可能です。ただし、
年度途中の入園は、転園などによる空きが出た場合のみ募集されるため、枠は非常に少ないのが一般的です。
希望する場合は、毎月自治体のホームページで空き状況をこまめにチェックし、募集があればすぐに申し込めるように準備しておく必要があります。
3. 「早生まれ(1〜3月生まれ)は不利」は本当?知っておきたい対策
「早生まれは保活で不利になる」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは本当なのでしょうか?その理由と対策について解説します。
3-1. なぜ早生まれは不利と言われるの?2つの理由
早生まれが不利と言われるのには、主に2つの理由があります。
- 理由1:0歳児クラス4月入園の申し込み時期に生まれていない
- 0歳児クラスの4月入園は、募集人数が最も多く入りやすいと言われています。しかし、その申し込みは前年の秋頃に行われるため、1月〜3月生まれの子どもは申し込み時点ではまだ生まれていません。多くの自治体では出産予定でも申し込み可能ですが、すでに出生している子どもが優先される場合があります。
- 理由2:激戦区の1歳児クラスからのスタートになりやすい
- 0歳児クラスの4月入園を逃すと、次のチャンスは1歳児クラスの4月入園になります。1歳児クラスは、0歳児クラスからの進級組で定員の多くが埋まってしまうため、
新規の募集枠が非常に少なく、競争率が格段に上がります。
3-2. 【生まれ月別】早生まれの保活戦略
生まれ月によって、取れる戦略は少し異なります。
- 1月生まれの場合:0歳児クラス4月入園も可能!
- 1月生まれの場合、生後3ヶ月で4月を迎えることになります。低月齢での入園に抵抗がなければ、出産予定で0歳児クラスの4月入園に申し込むのが最もおすすめです。
- 2月・3月生まれの場合:年度途中入園 or 1歳児クラス4月入園が基本
- 生後間もない状態での4月入園は現実的ではないため、育休を延長し、空きを狙って年度途中での入園を目指すか、1歳児クラスの4月入園を目標にするのが基本的な戦略となります。
3-3. 早生まれでも希望の園に入るための3つのポイント
早生まれでも諦める必要はありません。以下の3つのポイントを押さえて、戦略的に保活を進めましょう。
- ポイント1:認可外保育園や小規模保育園も視野に入れる
認可保育園だけに絞らず、認可外保育園や0〜2歳児対象の小規模保育園も併せて検討しましょう。これらの施設は、比較的入りやすい場合があります。特に小規模保育園を卒園すると、連携する認可保育園への優先入園枠が設けられている場合があり、3歳以降の預け先を確保しやすくなるメリットもあります。 - ポイント2:加点項目をチェックして点数を上げる
自治体の「調整指数」の項目を隅々まで確認し、少しでも点数を上げられないか検討しましょう。例えば、認可外保育園に預けている実績が加点対象になる自治体もあります。その場合、まずは認可外に預けて点数を稼ぎ、翌年度に認可保育園への転園を目指すという戦略も有効です。 - ポイント3:自治体の保育課に相談してみる
保活で悩んだら、一人で抱え込まずにお住まいの自治体の保育課(子育て支援課など)に相談してみましょう。地域の保育園事情に詳しい専門家から、具体的なアドバイスをもらえることがあります。早生まれであることの不安や、自身の状況を正直に話してみることをおすすめします。
4. 妊娠中にやるべきことリスト!無理なく進める保活5ステップ
体調が安定している妊娠中は、保活を進める絶好のチャンスです。出産後の負担を減らすためにも、無理のない範囲で以下の5つのステップを進めてみましょう。
4-1. STEP1:まずは夫婦で方針を話し合おう
保活は、夫婦で協力して進めることが何よりも大切です。まずは以下の点について、お互いの希望や考えを共有しましょう。
- いつから復職したいか
- どんな保育園に預けたいか(教育方針、規模など)
- 送迎の分担はどうするか
- 保育料はいくらまで許容できるか
ここで方針をすり合わせておくと、その後の情報収集や園選びがスムーズに進みます。
4-2. STEP2:情報収集を始めよう
夫婦で話し合った方針をもとに、具体的な情報収集を始めます。
-
自治体のホームページをチェック
お住まいの自治体のホームページには、保育園の一覧、入園のしおり、申込スケジュール、点数計算表など、保活に必要な情報がすべて掲載されています。まずはここを徹底的に読み込みましょう。 - 保育園検索サイトやアプリを活用する
地図上から近くの保育園を探したり、条件で絞り込んだりできるサイトやアプリを活用すると、効率的に情報収集ができます。
4-3. STEP3:自分の「点数」を計算してみよう
自治体のホームページにある点数計算表(利用調整基準表)をもとに、自分の世帯の点数を計算してみましょう。これにより、自分たちがどのくらいの位置にいるのかを客観的に把握でき、どのくらいの競争率の園まで狙えるかの目安になります。
4-4. STEP4:候補の保育園をリストアップしよう
情報収集した内容をもとに、通えそうな範囲にある保育園をいくつかリストアップします。自宅からの距離だけでなく、駅からの距離、通勤経路なども考慮して、
現実的に送迎が可能な園を10〜20園ほど挙げておくと安心です。
4-5. STEP5:体調の良い日に見学に行ってみよう
リストアップした園の中から、特に気になる園の見学予約を入れましょう。
妊娠中であれば、身軽に動けるうちに見学を済ませておくのがおすすめです。
実際に園の雰囲気や先生、子どもたちの様子を見ることで、パンフレットだけではわからない多くの情報を得ることができます。
【見学時のチェックリスト例】
- 園全体の雰囲気は明るいか
- 子どもたちは楽しそうに過ごしているか
- 先生たちの表情や子どもへの接し方はどうか
- 施設は清潔で、安全対策はされているか
- 園庭の有無や広さ
- 給食は園内で調理されているか(アレルギー対応は可能か)
- 延長保育の時間や料金、利用条件
- 保護者が参加する行事の頻度
5. 失敗しない保育園選びの5つのチェックポイント
数ある保育園の中から、わが子に合った園を選ぶにはどうすれば良いのでしょうか。後悔しないための5つのチェックポイントをご紹介します。
5-1. ポイント1:通いやすさ(自宅や職場からの距離)
毎日のことなので、送迎のしやすさは非常に重要なポイントです。
自宅からの距離はもちろん、最寄り駅や職場からのアクセスも確認しましょう。雨の日や子どもの体調が悪い日でも、無理なく通えるかどうかを具体的にシミュレーションしてみることが大切です。
5-2. ポイント2:保育時間と延長保育の有無
基本的な保育時間と、延長保育が何時まで可能か、利用条件や料金
も必ず確認しましょう。仕事の繁忙期や急な残業に対応できるかどうかは、仕事と育児を両立する上で欠かせないポイントです。
5-3. ポイント3:園の雰囲気や保育方針
園によって、「のびのび系」「お勉強系」など、保育方針は様々です。見学などを通して、
園長先生や保育士の考え方、子どもたちの過ごす様子
などを確認し、自分たちの教育方針や子どもの性格に合っているかを見極めましょう。
5-4. ポイント4:給食・アレルギー対応
給食が自園調理か、外部委託(センター給食)かを確認しましょう。アレルギーがある場合は、どの程度個別に対応してもらえるのか
を具体的に質問しておくことが重要です。
5-5. ポイント5:安全対策と衛生管理
子どもの命を預ける場所として、安全・衛生管理は最も重視すべきポイントです。
不審者対策(施錠、防犯カメラなど)、災害時の避難計画、おもちゃや施設の清掃状況などを、見学時にしっかりとチェックしましょう。
6. 保活に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、保活を進める上で多くの人が疑問に思う点についてお答えします。
Q. 育休はいつまで取れますか?
Q. 認可保育園に落ちたら(待機児童になったら)どうすればいいですか?
万が一、認可保育園の選考にすべて落ちてしまった場合でも、選択肢はいくつかあります。
- 認可保育園の二次募集に申し込む
- 認可外保育施設を探す
- 育児休業を延長する
- ベビーシッターや一時預かりなどを利用する
すぐに諦めず、早めに次の手を打つことが大切です。
Q. 見学の予約はいつ頃するのがベストですか?
Q. 申し込みに必要な書類は何ですか?
一般的に、以下のような書類が必要になります。自治体によって異なるため、必ず事前に確認してください。
- 入園申込書
- 就労(内定)証明書(両親分)
- 世帯の所得を証明する書類(課税証明書など)
- 世帯全員の住民票
- 母子手帳の写し
まとめ:計画的な保活で、安心して出産を迎えよう
保活は情報戦ですが、
正しい知識とスケジュール感を持って、妊娠中から少しずつ準備を進めることが成功のカギです。
何から手をつければ良いかわからない、という不安な気持ちが、この記事を読んで少しでも軽くなっていれば幸いです。
早生まれの不安や、初めてのことでわからないことだらけだと思いますが、
大切なのは完璧を目指すことではなく、ご自身の家庭に合った選択をすることです。
この記事を参考に、ご自身のペースで一歩ずつ進めていきましょう。あなたの保活がうまくいくことを心から応援しています。
まずは、お住まいの地域にどんな保育園があるか探すところから始めてみませんか?保育園検索サイト「エンクル」なら、地図から簡単に園を探し、気になる園をリスト化して比較検討できます。見学予約もサイトから可能です。さっそくサイトにアクセスして、あなたの保活の第一歩を踏み出しましょう。
理想の保育園・幼稚園探しなら「エンクル」 検索して地図上で空き情報を一括比較!口コミや見学予約機能も。登録した希望条件でオファーも届く!
保育園探しはプロにお任せ!希望の園探しをトコトンお手伝いします!
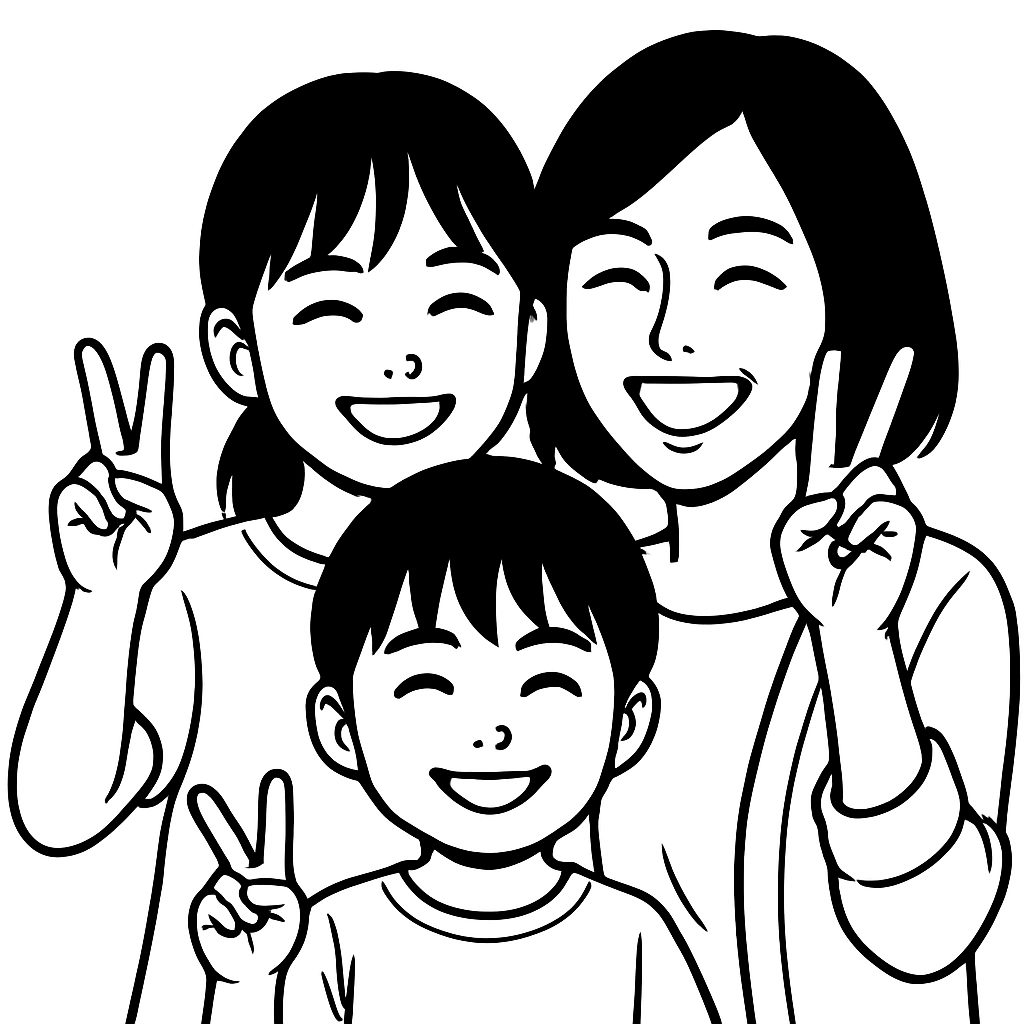
保活アドバイザーのもっちゃんです。小3の娘と年少の息子を育てる2児の母。保育園の転園を経験し、実体験をもとに保活&子育て情報を発信中。癒しは愛猫とのまったり時間です。








