育休が明け、いよいよ職場復帰。期待と同時に「仕事と育児、本当に両立できるかな?」「もし子どもが熱を出したらどうしよう…」といった大きな不安を抱えていませんか?特に、子どもの急な体調不良は、多くの先輩ママが直面してきた大きな壁です。職場に迷惑をかけたくない、でも子どものそばにいてあげたい…その板挟みで、復帰早々に心が折れそうになる方も少なくありません。
しかし、心配しすぎる必要はありません。この記事では、先輩ママたちがどのようにしてその壁を乗り越えてきたのか、具体的な方法を徹底解説します。そして、いざという時の強い味方になる「病児保育」という選択肢について、その内容から使い方まで詳しくご紹介します。この記事を読み終える頃には、あなたの復帰に対する不安が「これなら大丈夫!」という自信に変わっているはずです。
目次
- 1. 育休明けの職場復帰、本当のところは?先輩ママが直面するリアルな壁
- 2. 仕事と育児の両立で最大の壁は「子どもの急な体調不良」
- 3. 子どもの急な発熱でも仕事を休まない選択肢「病児保育」とは?
- 4. いざという時のために!病児保育の利用方法と選び方
- 5. 病児保育だけじゃない!仕事と育児を両立させるための5つのコツ
- 6. 「保育園はかわいそう?」は誤解!知っておきたい保育園のメリット
- 7. まとめ:仕事と育児の両立は「頼れる先」を見つけることから始めよう
1. 育休明けの職場復帰、本当のところは?先輩ママが直面するリアルな壁
職場復帰後の生活は、想像以上に変化が大きいものです。まずは、先輩ママたちが実際にどのような「壁」に直面したのか、リアルな声を見ていきましょう。
壁1:子どもの体調不良
「入園後、毎週のように熱を出す…有給がすぐになくなった」
壁2:想像以上に進まない仕事
「時短勤務なのに業務量は同じ。結局、家に持ち帰って深夜まで作業…」
壁3:夫婦間のすれ違い
「『手伝う』と言ってくれた夫。でも、結局ワンオペ育児で喧嘩が増えた」
壁4:自分の時間がない
「朝から晩まで全力疾走。気づけば1日誰とも話さず、孤独を感じる…」
壁5:周囲からのプレッシャー
「『子どもがかわいそう』という言葉に罪悪感を感じてしまう」
2. 仕事と育児の両立で最大の壁は「子どもの急な体調不良」
先輩ママの声にもあったように、両立における最大の壁は「子どもの急な体調不良」です。なぜなら、こればかりは予測もコントロールもできないからです。
2-1. なぜ「子どもの体調不良」が最大の壁になるのか?
子どもの急な体調不良が仕事と育児の両立を困難にする理由は、主に以下の4つです。
- 保育園からの突然の呼び出し電話
重要な会議中や締め切り直前など、タイミングを選ばずに電話はかかってきます。 - 仕事を休むことへの罪悪感と焦り
「また休むのか…」と同僚に申し訳なく感じたり、仕事の遅れに焦ったりしてしまいます。 - 看病による自身の疲労と睡眠不足
夜中の看病で寝不足になり、心身ともに疲れ果ててしまいます。 - 有給休暇の消費
子どもの看病で有給休暇を使い果たし、いざという時に休めなくなる不安があります。
2-2. 「仕事を休む」以外の選択肢を知っておく重要性
毎回仕事を調整するのは、精神的にもキャリア的にも大きな負担となります。だからこそ、復帰前に「仕事を休む」以外の選択肢を知り、準備しておくことが、あなたと家族、そして職場を守ることに繋がるのです。
3. 子どもの急な発熱でも仕事を休まない選択肢「病児保育」とは?
そこで知っておきたいのが「病児保育」というサービスです。これは、子どもが病気や病気の回復期で、保育園や学校には行けないけれど、保護者が仕事などの理由でそばにいられない場合に、一時的に子どもを預かってくれる施設やサービスのことです。
3-1. 病児保育にはどんな種類があるの?2つのタイプを解説
病児保育には、主に2つのタイプがあります。それぞれの特徴を理解し、ご家庭に合ったものを選びましょう。
- 施設型(専用スペース型)
- 病院や保育園に併設された専用スペースで預かるタイプです。看護師や保育士が常駐しているため、安心して預けられます。
- 訪問型(居宅訪問型)
- ベビーシッターなどが自宅に来て、1対1で看病してくれるタイプです。子どもは住み慣れた環境で過ごせるため、心身の負担が少ないのがメリットです。
3-2. 病児保育はいつから利用できる?対象年齢と症状の目安
多くの施設で生後6ヶ月頃から小学校低学年までを対象としています。ただし、施設によって異なるため、事前の確認が必要です。
また、預けられる症状にも目安があります。例えば、「38.5℃以下の発熱」「下痢や嘔吐が落ち着いている」など、施設ごとに基準が設けられています。利用前にかかりつけ医の診察を受け、連絡票などを記入してもらうのが一般的です。
3-3. 病児保育の費用は?料金相場と補助金について
料金はタイプや地域によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
| 種類 | 料金相場(1日あたり) | 特徴 |
|---|---|---|
| 施設型 | 2,000円~5,000円 | 看護師・保育士が常駐で安心。他の子と一緒の場合も。 |
| 訪問型 | 15,000円~25,000円(時給2,000円~3,000円) | 自宅で1対1のケア。費用は高めだが、子どもの負担が少ない。 |
お住まいの自治体によっては利用料の助成制度があるため、市区町村のウェブサイトを必ず確認してみましょう。
4. いざという時のために!病児保育の利用方法と選び方
病児保育は、いざという時にスムーズに利用できるよう、事前の登録や準備が不可欠です。ここでは、具体的なステップと選び方のポイントをご紹介します。
4-1. STEP1:お住まいの地域の病児保育施設を探す
まずは、利用できる施設を探すことから始めましょう。
- 自治体のウェブサイトで探す
「〇〇市 病児保育」などで検索すると、公式情報が見つかります。 - 「病児保育ネット」などの検索サイトを活用する
全国の施設をまとめて検索できるサイトも便利です。
4-2. STEP2:事前に施設登録・面談を済ませておく
ほとんどの施設で事前登録が必要です。子どもが元気な時に、必要な書類を揃えて登録を済ませておきましょう。施設によっては簡単な面談がある場合もあります。
4-3. STEP3:利用の流れをシミュレーションしておく
いざという時に慌てないよう、利用の流れを頭に入れておきましょう。
- 予約方法
電話予約か、ネット予約かを確認しておきます。 - 必要な持ち物リスト
保険証、母子手帳、着替え、おむつ、ミルク、薬、お弁当など、必要なものをリストアップしておくと安心です。 - かかりつけ医の受診
利用前に受診が必要な場合がほとんどです。医師に連絡票を記入してもらう流れも確認しておきましょう。
4-4. 失敗しない病児保育施設の選び方【チェックリスト】
複数の施設を比較検討する際は、以下のポイントをチェックしましょう。
- [ ] 自宅や職場からのアクセスは良いか?
- [ ] 看護師や保育士の体制は万全か?
- [ ] 施設の衛生環境はどうか?
- [ ] 予約のしやすさ、キャンセル規定は?
- [ ] 利用者の口コミや評判は?
5. 病児保育だけじゃない!仕事と育児を両立させるための5つのコツ
病児保育というお守りを手に入れたら、次は日々の生活をスムーズにするための工夫です。少しの意識で、心と体の負担は大きく減らせます。
5-1. コツ1:夫婦で「チーム」になるための役割分担
復帰前に、夫婦で家事育児のタスクをすべて書き出し、「見える化」しましょう。その上で、どちらが担当するかを話し合います。おむつ替えや寝かしつけといった分かりやすいタスクだけでなく、「トイレットペーパーの補充」や「献立を考える」といった「名もなき家事」もリストアップするのがポイントです。
5-2. コツ2:完璧を目指さない!「やらないことリスト」を作る
すべてを完璧にこなそうとすると、必ず無理が生じます。「夕食は週2回お惣菜OK」「掃除は週末だけ」など、意識的に手を抜くポイントを決めておくことで、心の負担が軽くなります。
5-3. コツ3:テクノロジーを味方につける(時短家電・ネットスーパー)
食洗機、乾燥機付き洗濯機、ロボット掃除機は、ワーキングマザーの「三種の神器」です。初期投資はかかりますが、その後の時間的・精神的な余裕を考えれば、決して高い買い物ではありません。ネットスーパーや食材宅配サービスも積極的に活用しましょう。
5-4. コツ4:会社の制度を最大限に活用する
時短勤務、子の看護休暇、在宅勤務など、利用できる制度は遠慮なく使いましょう。これらは労働者の権利です。制度をうまく活用することで、無理なく働き続けることができます。
5-5. コツ5:自分をケアする時間を意識的に作る
たった15分でも構いません。子どもが寝た後に好きな音楽を聴く、通勤中にゆっくりお茶を飲むなど、意識的に自分を甘やかす時間を作りましょう。ママが笑顔でいることが、家族にとって一番の幸せです。
6. 「保育園はかわいそう?」は誤解!知っておきたい保育園のメリット
職場復帰にあたり、「こんなに小さい頃から預けてかわいそうかな…」と罪悪感を抱く必要は全くありません。保育園には、家庭だけでは得られない素晴らしいメリットがたくさんあります。
6-1. 保育園に通う子どものメリット
- 社会性や協調性が身につく
お友達との関わりの中で、順番を待つことや思いやりの心を学びます。 - 生活リズムが整う
毎日決まった時間に食事や昼寝をすることで、規則正しい生活習慣が身につきます。 - 専門家による発達のサポートが受けられる
保育士は子どもの発達のプロです。一人ひとりの成長に合わせた適切な関わりをしてくれます。 - たくさんの遊びや経験ができる
家庭ではなかなかできないダイナミックな遊びや、季節の行事などを通して豊かな経験ができます。
6-2. 保育園を利用する親のメリット
- 自分のキャリアを継続できる
仕事を通して社会との繋がりを持ち続けることができます。 - 育児の悩みを保育士に相談できる
経験豊富な保育士は、育児における心強いパートナーになります。 - 親自身の心と時間に余裕が生まれる
子どもと少し離れる時間を持つことで、心に余裕が生まれ、より愛情深く接することができます。 - ママ友・パパ友との繋がりができる
同じ立場の保護者と悩みを共有したり、情報交換したりできる貴重な場になります。
7. まとめ:仕事と育児の両立は「頼れる先」を見つけることから始めよう
職場復帰と育児の両立は、決して一人で乗り越えるものではありません。病児保育のようなサービス、夫婦の協力、そして何より、日常的にお子さんを安心して預けられる保育園という「頼れる先」を見つけることが、両立成功の第一歩です。
まずは、あなたとお子さんにぴったりの保育園探しから始めてみませんか?
「エンクル」なら、お住まいの地域やこだわりの条件から、簡単に保育園を検索・比較できます。気になる園が見つかったら、サイトからそのまま見学予約も可能。忙しいあなたの保活を、エンクルが力強くサポートします。まずは、どんな保育園があるか、気軽に検索してみてください。
理想の保育園・幼稚園探しなら「エンクル」 検索して地図上で空き情報を一括比較!口コミや見学予約機能も。登録した希望条件でオファーも届く!
保育園探しはプロにお任せ!希望の園探しをトコトンお手伝いします!
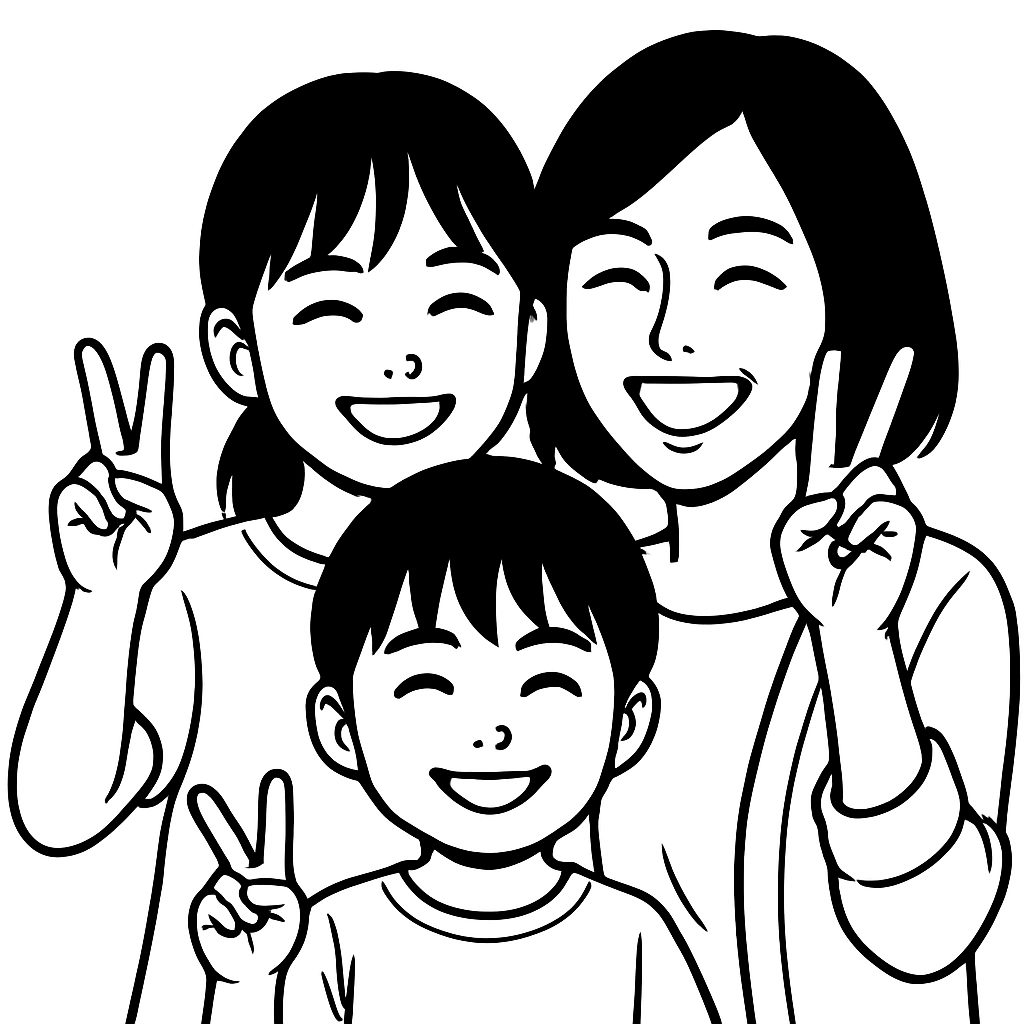
保活アドバイザーのもっちゃんです。小3の娘と年少の息子を育てる2児の母。保育園の転園を経験し、実体験をもとに保活&子育て情報を発信中。癒しは愛猫とのまったり時間です。










