
「育休からの職場復帰、そろそろ考えなきゃ…でも、復帰日っていつにすればいいの?」
「保育園のこともあるし、お金で損したくない。会社への挨拶もどうしよう…」
初めての育休復帰を前に、何から手をつけていいか分からず、たくさんの不安を抱えていませんか?
復帰日の決め方一つで、家計や子どもの生活、職場との関係、そして復帰後の働きやすさが大きく変わるため、慎重に考えたいですよね。
ご安心ください。この記事では、初めての復帰でも失敗しないよう、復帰までの全ステップを時系列で徹底解説します。
お金で損しない復帰タイミングはもちろん、職場へのスマートな挨拶の仕方や、先輩ママが実践する両立のコツまで、あなたの不安をすべて解消します。一緒に準備を進めて、自信を持って新しいスタートを切りましょう。
目次
- 1. 【全体像】育休復帰までのやることリスト&モデルスケジュール
- 1-1. 育休復帰 半年前〜1ヶ月前のモデルスケジュール(表形式)
- 1-2. これで完璧!育休復帰 やることチェックリスト
- 2. 育休復帰日を決める4つのステップ
- 2-1. STEP1:子どもの預け先を決める(保活の開始)
- 2-2. STEP2:会社へ復帰の意思を伝え、相談する
- 2-3. STEP3:復帰日を具体的に決める3つのポイント
- 2-4. STEP4:復帰日を正式に報告し、手続きを進める
- 3. 【印象アップ】復帰前の挨拶と報告のポイント
- 3-1. 挨拶はいつ、誰にすべき?タイミングと相手
- 3-2. 挨拶で伝えるべき内容【そのまま使える例文付き】
- 3-3. 手土産は必要?おすすめの品と渡し方のマナー
- 3-4. *コラム:よくある失敗談①「挨拶でこれをやったら気まずくなった…」*
- 4. 先輩ママに聞く!復帰後の仕事と育児を両立させる5つのコツ
- 4-1. コツ1:完璧を目指さない!家事のハードルを下げる
- 4-2. コツ2:夫婦で家事育児の分担を「見える化」する
- 4-3. コツ3:便利なサービス・家電を積極的に活用する(宅配、食洗機など)
- 4-4. コツ4:1日のタイムスケジュールをシミュレーションしておく
- 4-5. コツ5:病児保育など「もしも」の時の預け先を確保しておく
- 5. 育休復帰に関するよくある質問(Q&A)
- 6. まとめ:計画的な準備で、安心して育休から復帰しよう
1. 【全体像】育休復帰までのやることリスト&モデルスケジュール
育休からの復帰は、やることがたくさんあって何から手をつければ良いか分からなくなりがちですよね。まずは全体像を把握して、計画的に進めていきましょう。ここでは、一般的なモデルスケジュールと、やるべきことをまとめたチェックリストをご紹介します。
1-1. 育休復帰 半年前〜1ヶ月前のモデルスケジュール(表形式)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 復帰の半年前〜 | ・保育園の情報収集を開始(保活スタート) ・夫婦で復帰後の生活について話し合う ・会社の上司に復帰の意向を軽く伝えておく |
| 復帰の3ヶ月前 | ・保育園の見学、申し込み ・会社に復帰の意思を正式に伝え、面談 ・復帰後の働き方(時短勤務など)を相談・申請 |
| 復帰の2ヶ月前 | ・保育園の入園決定 ・会社へ復帰日を正式に報告 ・必要な書類(就労証明書など)の準備 |
| 復帰の1ヶ月前 | ・保育園の入園説明会、準備 ・復帰後の生活シミュレーション ・病児保育などの登録 |
| 復帰の1〜2週間前 | ・慣らし保育の開始 ・職場への挨拶 ・美容院に行くなど、自分の準備 |
1-2. これで完璧!育休復帰 やることチェックリスト
- [ ] 保育園の情報収集
- [ ] 保育園の見学・申し込み
- [ ] 夫婦での家事・育児分担の話し合い
- [ ] 会社の上司へ復帰意思の連絡・相談
- [ ] 復帰後の働き方(時短勤務など)の申請
- [ ] 会社への復帰日の正式報告
- [ ] 会社・保育園へ提出する書類の準備
- [ ] 慣らし保育のスケジュール調整
- [ ] 職場への挨拶(手土産の準備)
- [ ] 復帰後のタイムスケジュールのシミュレーション
- [ ] 病児保育など、緊急時の預け先の確保
- [ ] 便利な家電やサービスの導入検討
2. 育休復帰日を決める4つのステップ
全体像が掴めたら、いよいよ復帰日を決める具体的なステップに進みましょう。後悔しない復帰日を決めるためには、4つのステップを順番に進めていくのがおすすめです。
2-1. STEP1:子どもの預け先を決める(保活の開始)
復帰日を決める上で、最も重要で時間がかかるのが「保活」です。子どもの預け先が決まらないと、復帰日も決められませんよね。
保活はいつから始めるべき?
結論から言うと、できるだけ早く、できれば妊娠中から始めるのが理想です。しかし、産後からでも決して遅くはありません。
一般的に、多くの保育園は4月入園の枠が最も大きいため、4月入園を目指す場合は、前年の秋頃(9月〜11月)に申し込みが始まることが多いです。そのスケジュールから逆算して、夏頃までには情報収集や見学を済ませておくと安心です。
保育園探しで失敗しないためのポイント
保育園探しで後悔しないために、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 認可・認可外の違いを理解する
国の基準を満たした「認可保育園」と、自治体独自の基準で運営される「認可外保育園(認証保育所など)」があります。保育料や保育時間、サービス内容が異なるため、それぞれの特徴を理解しましょう。 - 見学には必ず行く
ホームページやパンフレットだけでは分からない、園の雰囲気や先生方、子どもたちの様子を自分の目で確かめることが大切です。 - 譲れない条件の優先順位を決める
「家からの距離」「保育時間」「園庭の有無」「食育へのこだわり」など、家庭にとって何が一番大切か、優先順位を決めておくと園を選びやすくなります。
園探しから見学予約まで!保活を効率化するサービス「エンクル」とは?
「育児をしながらたくさんの保育園情報を集めて、電話で見学予約するのは大変…」と感じていませんか?
そんな忙しいママ・パパにおすすめなのが、保育園・幼稚園探しサービス「エンクル」です。
- 地図から簡単検索
お住まいの地域や通勤経路など、地図を見ながら直感的に園を探せます。 - スマホで見学予約まで完結
気になる園が見つかったら、そのままWEB上で見学予約が可能。電話をかける手間が省けます。 - 園の情報をまとめて比較
お気に入り登録した園の情報を一覧で比較できるので、家族との相談もスムーズです。
育児の合間のスキマ時間を使って、効率的に保活を進めていきましょう。
2-2. STEP2:会社へ復帰の意思を伝え、相談する
子どもの預け先の目処が立ったら、次は会社への連絡です。円満な復帰のためには、早めの報告・相談が鍵となります。
いつ、誰に、何を伝えるべき?
復帰予定日の2〜3ヶ月前までには、直属の上司に直接伝えるのが一般的です。まずはメールや電話でアポイントを取り、面談の時間を設けてもらいましょう。
伝えるべき内容は以下の通りです。
- 育休取得への感謝
- 復帰の意思と、おおよその復帰希望時期
- 復帰後の働き方に関する希望(時短勤務など)
- (もしあれば)復帰にあたっての不安や相談事項
復帰後の働き方(時短勤務など)の希望を伝える
子どもが小さいうちは、時短勤務や残業免除などの制度を利用したいと考える方も多いでしょう。これらの制度を利用するには、会社の就業規則に定められた期日までの申請が必要です。面談の際に希望を伝え、必要な手続きについて確認しておきましょう。
コラム:先輩ママの体験談①「上司への相談、こう伝えたらスムーズでした!」
「ご無沙汰しております。育休中はご配慮いただき、ありがとうございます。おかげさまで、子どもも元気に育っております。さて、来春の職場復帰に向けて準備を始めたく、ご相談のお時間をいただけないでしょうか。復帰後の働き方についても、ご相談させていただけますと幸いです。」
このように、感謝の気持ちと前向きな姿勢を伝えることで、上司も快く相談に乗ってくれ、その後の手続きが非常にスムーズに進みました。
2-3. STEP3:復帰日を具体的に決める3つのポイント
会社との相談と並行して、具体的な復帰日を決定していきます。ここでは、絶対に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
【ポイント1:お金】社会保険料で損しないのは「月初復帰」
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)で損をしないためには、月初の復帰がおすすめです。
育休中の社会保険料は免除されていますが、復帰すると支払いが再開します。この社会保険料は日割り計算されず、「月末に会社に在籍しているか」でその月分の支払い義務が決まります。
例えば、5月30日に復帰しても、5月1日に復帰しても、支払う社会保険料は同じ1ヶ月分です。しかし、給料は日割り計算されるため、月の途中で復帰すると給料が少ないのに保険料は満額引かれてしまい、手取りがかなり少なくなってしまいます。
- 例:5月31日に復帰
- → 5月分の社会保険料が発生。給料は1日分。
- 例:6月1日に復帰
- → 5月分の社会保険料は免除。6月分から発生。
特別な事情がなければ、月初を復帰日に設定するのが最も経済的です。
【ポイント2:子ども】慣らし保育の期間(1〜2週間)を必ず考慮する
子どもが新しい環境に慣れるためには、「慣らし保育」の期間が必要です。初日は1〜2時間、翌日は午前中だけ…と、少しずつ保育時間を延ばしていきます。
この期間は、一般的に1週間〜2週間程度かかりますが、子どもの様子によってはもっと長くなることも。また、集団生活が始まるとすぐに体調を崩し、お休みすることも珍しくありません。
復帰日から逆算して、最低でも2週間は慣らし保育の期間として確保しておきましょう。有給休暇を組み合わせるなど、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
【ポイント3:手続き】会社の規定と保育園の入園日を確認する
最終的な復帰日を決める前に、会社と保育園、両方のルールを確認しましょう。
- 会社の規定
- 復帰に関する手続き(復職届の提出など)に締め切りはあるか。
- 保育園の入園日
- 月の途中からの入園が可能かどうかも確認が必要です。
これらの情報を総合的に判断し、最適な復帰日を決定します。
2-4. STEP4:復帰日を正式に報告し、手続きを進める
復帰日が決まったら、会社と保育園に正式に報告し、必要な手続きを進めます。書類の準備には時間がかかるものもあるため、早めに着手しましょう。
会社への提出が必要な書類リスト
- 育児休業復職届
- 健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届
- 保育所等入所証明書のコピー
- その他、会社独自の書類
保育園への提出が必要な書類リスト
- 入園申込書
- 就労証明書(会社に発行を依頼)
- 家庭状況を証明する書類(住民票など)
- その他、園が指定する書類
3. 【印象アップ】復帰前の挨拶と報告のポイント
復帰日が決まったら、職場への挨拶の準備も忘れずに行いましょう。丁寧な挨拶は、あなたの印象を良くし、復帰後のスムーズな人間関係に繋がります。
3-1. 挨拶はいつ、誰にすべき?タイミングと相手
復帰の1〜2週間前がベストなタイミングです。慣らし保育が始まって少し落ち着いた頃に、子どもを預けて身軽な状態で伺うのが良いでしょう。
挨拶に伺う相手は以下の通りです。
- 直属の上司
- 部署の同僚
- 人事部など、お世話になった部署
- 他部署でも関わりの深い方
事前に上司に連絡し、挨拶に伺う日時を調整しておくとスムーズです。
3-2. 挨拶で伝えるべき内容【そのまま使える例文付き】
挨拶では、以下の内容を簡潔に伝えましょう。
- 育休取得への感謝
- 復帰日と復帰後の働き方(時短勤務など)
- 復帰後の意欲
- 周りへの配慮と協力のお願い
【そのまま使える挨拶例文】
「ご無沙汰しております。〇月〇日より復職させていただくことになりました、〇〇です。
育休中は大変お世話になり、本当にありがとうございました。
復帰後は、当面の間、〇時までの時短勤務とさせていただきます。ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、早く戦力になれるよう精一杯頑張りますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。」
3-3. 手土産は必要?おすすめの品と渡し方のマナー
手土産は必須ではありませんが、用意しておくと感謝の気持ちが伝わりやすいでしょう。
- おすすめの品
- 部署の人数分より少し多めの、個包装で日持ちするお菓子がおすすめです。休憩中に気軽に食べられるものが喜ばれます。
- 渡し方のマナー
- 上司に挨拶した後、休憩時間などに「皆様で召し上がってください」と一言添えて渡しましょう。
3-4. コラム:よくある失敗談①「挨拶でこれをやったら気まずくなった…」
「久しぶりの職場で話が弾み、つい育児の苦労話や子どもの自慢話ばかりしてしまいました…。後から考えると、仕事モードの同僚たちには迷惑だったかもしれません。挨拶は簡潔に、仕事への前向きな姿勢を見せることが大切だと反省しました。」
4. 先輩ママに聞く!復帰後の仕事と育児を両立させる5つのコツ
復帰後の生活に不安を感じている方も多いはず。ここでは、先輩ワーママたちが実践している、仕事と育児を上手に両立させるためのコツを5つご紹介します。
4-1. コツ1:完璧を目指さない!家事のハードルを下げる
復帰後は、とにかく時間がありません。「平日の夕食は一汁一菜でOK」「掃除は週末にまとめて」など、家事のハードルをぐっと下げましょう。すべてを完璧にこなそうとすると、心も体も疲弊してしまいます。
4-2. コツ2:夫婦で家事育児の分担を「見える化」する
「言わなくてもやってくれるはず」という期待は禁物です。家事や育児のタスクをすべて書き出し、どちらが担当するかを明確に決めましょう。カレンダーアプリなどでスケジュールを共有するのもおすすめです。お互いの負担を理解し、協力体制を築くことが両立の鍵です。
4-3. コツ3:便利なサービス・家電を積極的に活用する(宅配、食洗機など)
時間をお金で買う、という発想も大切です。
- 食材宅配サービス
- ミールキット
- 食洗機
- 乾燥機付き洗濯機
- ロボット掃除機
これらを活用することで、時間に大きなゆとりが生まれます。
4-4. コツ4:1日のタイムスケジュールをシミュレーションしておく
復帰前に、平日の朝起きてから夜寝るまでのタイムスケジュールを一度シミュレーションしてみましょう。「朝の準備に思ったより時間がかかる」「この時間にこれをやるのは無理だ」など、課題が見えてきて、対策を立てることができます。
4-5. コツ5:病児保育など「もしも」の時の預け先を確保しておく
子どもは本当によく熱を出します。復帰していきなり欠勤が続くと、心苦しいですよね。そんな「もしも」の時のために、地域の病児保育施設やファミリー・サポート・センターなどに事前に登録しておくと、いざという時に慌てずに済みます。
5. 育休復帰に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、育休復帰に関してよく寄せられる質問にお答えします。
- Q. 復帰日を早めることはできますか?
- A. はい、可能です。
ただし、会社の繁忙期や人員配置の都合もあるため、まずは早めに上司に相談することが必要です。会社との合意があれば、当初の予定より早く復帰することができます。 - Q. 育休を延長することはできますか?
- A. はい、特定の条件下で可能です。
原則として、育児休業は子どもが1歳になるまでですが、「保育園に入れない」などの理由がある場合は、最長で子どもが2歳になるまで延長できます。延長を希望する場合は、会社への申請が必要です。 - Q. 夫(パパ)も育休を取得する場合、復帰日はどう考えればいいですか?
- A. 夫婦で時期をずらして取得するのがおすすめです。
例えば、ママの育休終了と同時にパパが育休を開始する「パパ・ママ育休プラス」制度を利用すれば、切れ目なく育児に専念できます。また、ママの復帰後の大変な時期にパパが育休を取得し、家事・育児をサポートするという形も良いでしょう。 - Q. 時短勤務はいつまで利用できますか?給料やボーナスはどうなりますか?
- A. 法律では子どもが3歳になるまで利用できます。
会社によっては、小学校就学前までなど、より長い期間利用できる独自の制度を設けている場合もあります。給料は、短縮した勤務時間分が減額されるのが一般的です。ボーナスについても、勤務時間に応じて減額されたり、評価期間中の実績に基づいて算定されたりします。詳しくは会社の就業規則を確認しましょう。
6. まとめ:計画的な準備で、安心して育休から復帰しよう
育休からの職場復帰は、あなたのキャリアにおける大きな転機です。不安も大きいと思いますが、一つひとつ準備を進めれば、きっと乗り越えられます。
最後に、この記事のポイントをまとめます。
- 復帰までの全体像とスケジュールを把握し、計画的に進める
- 復帰日は「お金」「子ども」「手続き」の3つのポイントで決める
- 復帰前の丁寧な挨拶が、円滑な人間関係の鍵
- 完璧を目指さず、夫婦やサービスを頼りながら両立を目指す
育休からの復帰は、期待と同時にたくさんの不安が伴うもの。ですが、一つひとつ情報を集め、計画的に準備を進めていけば、きっと大丈夫です。あなたとご家族にとってベストな形で、新しいスタートが切れるよう応援しています。
まずはその第一歩として、お住まいの地域の保育園探しから始めてみませんか?
理想の保育園・幼稚園探しなら「エンクル」 検索して地図上で空き情報を一括比較!口コミや見学予約機能も。登録した希望条件でオファーも届く!
保育園探しはプロにお任せ!希望の園探しをトコトンお手伝いします!
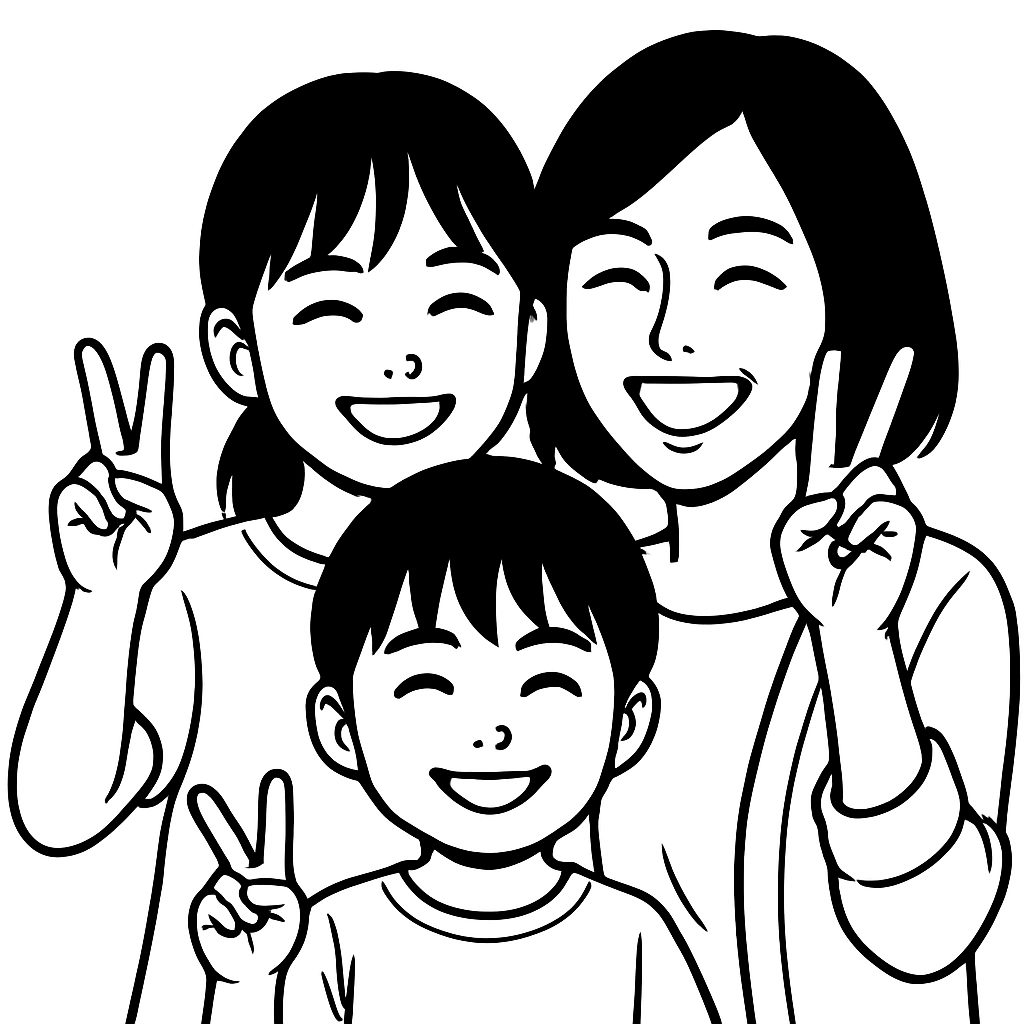
保活アドバイザーのもっちゃんです。小3の娘と年少の息子を育てる2児の母。保育園の転園を経験し、実体験をもとに保活&子育て情報を発信中。癒しは愛猫とのまったり時間です。







