
ご懐妊おめでとうございます!新しい命の訪れという大きな喜びに包まれる一方で、「職場への報告、いつ、誰に、どうやって伝えよう…」「円満に進めたいけど、迷惑はかけたくない…」そんな不安や悩みを抱えていませんか?
報告の仕方一つで、その後のマタニティライフや職場との関係が大きく変わることも。でも、ご安心ください。
この記事を読めば、報告の不安が解消され、職場から心から応援されながら円満に産休・育休を迎えることができます。報告の最適なタイミングから、そのまま使える具体的な例文、報告後の手続きや保活の始め方まで、あなたの疑問と不安を1記事でまるごと解消します。
一緒に、安心してマタニティライフを送るための準備を始めましょう。
【この記事でわかること】
1. 【いつ?】職場への妊娠報告、最適なタイミングと順番は?
2. 【何を?】報告前に準備すべき5つのことリスト
3. 【どう伝える?】そのまま使える!言い方・伝え方パーフェクト例文集
4. 円満な報告のために知っておきたい3つの心構え
5. 【報告後に】知っておくと安心!産休・育休の手続きと「保活」の始め方
6. 職場への妊娠報告に関するQ&A
目次
- 1. 【いつ?】職場への妊娠報告、最適なタイミングと順番は?
- 2. 【何を?】報告前に準備すべき5つのことリスト
- 3. 【どう伝える?】そのまま使える!言い方・伝え方パーフェクト例文集
- 4. 円満な報告のために知っておきたい3つの心構え
- 5. 【報告後に】知っておくと安心!産休・育休の手続きと「保活」の始め方
- 6. 職場への妊娠報告に関するQ&A
1. 【いつ?】職場への妊娠報告、最適なタイミングと順番は?
職場への妊娠報告で最も悩むのが「いつ、誰に言うか」というタイミングと順番です。ここでは、多くの人が実践している一般的な目安と、その理由について解説します。
1. 結論:安定期に入る「妊娠4〜5ヶ月頃」が一般的
妊娠報告の最適なタイミングは、一般的に安定期に入る妊娠4〜5ヶ月(12週〜19週頃)が目安とされています。
この時期が推奨されるのには、主に2つの理由があります。
- 流産のリスクが低減する
妊娠初期は残念ながら流産のリスクが比較的高いため、赤ちゃんの心拍が確認でき、状態が安定してから報告する方が安心です。 - つわりが落ち着き、体調が安定してくる
心身ともに落ち着いた状態で、今後の働き方や引き継ぎについて具体的に相談しやすくなります。
ただし、つわりがひどい場合や、立ち仕事・力仕事など身体に負担のかかる業務の場合は、母子の安全を最優先し、安定期を待たずに早めに上司に相談することが重要です。
2. 報告する順番は「直属の上司」が最初
妊娠報告は、必ず「直属の上司」に一番最初に行いましょう。
会社の同僚や先輩に先に話してしまうと、噂話として上司の耳に入ってしまう可能性があります。そうなると、正式な報告がしづらくなり、上司との信頼関係にも影響しかねません。
業務の調整や人員の補充、産休・育休中の引き継ぎなどを最初にお願いするのは直属の上司です。まずは上司に報告し、その後の同僚や他部署への報告のタイミングや方法についても相談の上で進めるのが、最もスムーズで円満な進め方です。
3. 相手別|最適な報告タイミングの目安
報告する相手によっても、適切なタイミングは異なります。一般的な目安をまとめました。
- 直属の上司:妊娠4ヶ月以降、安定期に入る頃
- 前述の通り、安定期に入ったタイミングで一番最初に報告します。今後の業務調整や産休・育休の取得について相談を始めましょう。
- 同僚・チームメンバー:妊娠5ヶ月頃、上司と相談してから
- 上司への報告後、許可を得てから同僚やチームメンバーに伝えます。一般的には、お腹のふくらみが少しずつ目立ち始める5ヶ月頃が目安です。業務の引き継ぎなどで直接関わることになるため、早めに伝えることで、協力を得やすくなります。
- 人事・総務部:上司への報告と同時期か、指示に従う
- 産休・育休の手続きや社会保険関連の申請窓口となる部署です。上司に報告した後、その指示に従って手続きを進めましょう。上司によっては、一緒に人事部へ報告に行ってくれる場合もあります。
- 社外・取引先:産休に入る1ヶ月前を目安に
- 担当業務の後任者を紹介し、安心して引き継ぎを行う期間を考慮して、産休に入る1ヶ月前までには報告するのが一般的です。これも上司と相談して、適切なタイミングを決めましょう。
2. 【何を?】報告前に準備すべき5つのことリスト
上司に妊娠報告をする際は、今後の見通しを伝えることで、上司も具体的な対応を検討しやすくなります。報告の場でスムーズに話を進めるために、以下の5つの項目を事前に整理しておきましょう。
- 準備1:出産予定日
- 産休・育休の期間を計算する上で最も重要な情報です。母子手帳などで正確な日付を確認しておきましょう。
- 準備2:産休・育休の取得希望期間
- いつから産休に入り、いつ頃まで育休を取得したいのか、現時点での希望を伝えられるようにしておきましょう。会社の就業規則を確認し、制度について理解しておくと話がスムーズです。
- 準備3:復職の意思と希望する働き方
- 産休・育休後に復職する意思があるかどうかは、会社にとって非常に重要な情報です。復職を希望する場合はその旨を明確に伝えましょう。また、復帰後に時短勤務などを希望する場合は、その可能性についても相談できるとベストです。
- 準備4:現在の体調と業務で配慮してほしいこと
- つわりの状況や、通勤ラッシュを避けるための時差出勤、力仕事や長時間の立ち仕事を避けたいなど、体調面で配慮してほしいことがあれば具体的に伝えましょう。無理は禁物です。
- 準備5:引き継ぎ内容の簡単なリストアップ
- 自分が担当している業務内容を簡単に書き出しておくと、今後の引き継ぎ計画について相談しやすくなります。「この業務は〇〇さんにお願いしたいと考えています」といった具体的な提案ができると、上司も安心するでしょう。
3. 【どう伝える?】そのまま使える!言い方・伝え方パーフェクト例文集
準備が整ったら、いよいよ報告です。ここでは、相手や状況に応じた具体的な言い方や伝え方の例文をご紹介します。
1. 基本マナー:まずは「口頭」で直接伝えるのがベスト
妊娠は非常にプライベートで大切な報告です。可能な限り、メールやチャットではなく、対面で直接伝えるのが最も丁寧で誠意が伝わります。
上司に報告する際は、「少しご相談したいことがあるのですが、10分ほどお時間をいただけますでしょうか」と事前にアポイントを取り、会議室など他の人に話を聞かれない場所で報告しましょう。
2. 【上司への報告】口頭での伝え方と例文
- おめでたい報告ですが、まずは「私事で恐縮ですが」と切り出すのがマナーです。
- 事前に準備した5つの項目を簡潔に伝えます。
- 仕事への意欲と、周囲への感謝・配慮の気持ちを伝えます。
【例文】
〇〇部長、お時間をいただきありがとうございます。
私事で大変恐縮なのですが、このたび新しい命を授かりました。現在妊娠〇ヶ月で、出産予定日は〇月〇日です。
体調は良好で、今後の業務もこれまで通り精一杯務めさせていただきます。
産休・育休については、〇月頃から取得させていただきたいと考えております。
産後は復職し、またこちらで働きたいと思っておりますので、不在の間、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。
引き継ぎにつきましても、責任をもってしっかり行いますので、改めてご相談させていただけますでしょうか。
3. 【上司への報告】やむを得ずメールで伝える場合の例文
リモートワークなどで直接会うのが難しい場合は、メールで報告することになります。その際も、メールを送った後に電話で補足説明をするなど、丁寧な対応を心がけましょう。
件名:【〇〇(氏名)】ご報告
本文:
〇〇部長
お疲れ様です。〇〇です。
本来であれば直接お伝えすべきところ、メールでのご連絡となり大変申し訳ございません。
私事で恐縮ですが、このたび第一子を授かりましたのでご報告させていただきます。
現在妊娠〇ヶ月で、出産予定日は〇月〇日です。
今後の働き方や産休・育休の取得につきまして、近いうちにご相談させていただきたく、別途お時間をいただけますでしょうか。
まずはご報告までと思い、ご連絡いたしました。
引き続き、業務に支障がないよう努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
4. 【同僚・チームへの報告】朝礼やミーティングでの伝え方と例文
上司の許可を得てから、朝礼やチームミーティングの場で同僚に報告します。
【例文】
皆さん、少しお時間をいただき失礼します。
私事で恐縮ですが、このたび子どもを授かりました。
〇月から産休に入らせていただく予定です。
それまでの間、これまで通り業務に励みますので、どうぞよろしくお願いいたします。
産休中はご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、引き継ぎはしっかり行いますので、ご協力いただけますと幸いです。
5. 【全社への報告】メールで伝える場合の例文
上司や人事部の指示があった場合に、全社や部署全体へメールで報告します。
件名:産休・育休取得のご挨拶【〇〇(氏名)】
本文:
関係者の皆様
お疲れ様です。〇〇部の〇〇です。
この度、〇月〇日の出産に備え、〇月〇日より産休に入らせていただくことになりました。
最終出社日は〇月〇日の予定です。
産休中の業務につきましては、後任の〇〇さんにお願いしております。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
まずはメールにて失礼いたします。
6. 【NEW】チャットツール(Slack/Teams)で伝える場合の例文
普段からチャットでのコミュニケーションが中心の職場では、チャットで報告することもあるでしょう。カジュアルなツールですが、丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。
【例文】
@team(チームメンション)
皆さん、お疲れ様です。〇〇です。
私事で恐縮ですが、このたび妊娠いたしましたのでご報告します。
産休に入るまでは、引き続き業務に励みますので、どうぞよろしくお願いします。
不在中の業務については、後日改めて共有させていただきます。
体調によってご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、温かく見守っていただけると嬉しいです。
7. これはNG!円満報告のために避けるべき伝え方・表現
- 「権利だから」という態度
産休・育休は労働者の権利ですが、それを前面に出すのは避けましょう。周囲への感謝と配慮の気持ちが大切です。 - 曖昧な報告
「いつ頃復帰するか分かりません」など、今後の見通しが曖昧すぎると、会社側も対応に困ってしまいます。現時点での希望を伝えましょう。 - SNSでの先行報告
職場に伝える前にSNSで報告するのは絶対にNGです。必ず直属の上司への報告を最優先してください。 - 突然の報告
「来週から休みます」といった直前の報告は、引き継ぎが間に合わず、職場に大きな混乱を招きます。計画的に報告しましょう。
4. 円満な報告のために知っておきたい3つの心構え
報告の言葉選びやタイミングも重要ですが、それ以上に大切なのがあなたの「心構え」です。円満なマタニティライフを送るために、以下の3つの姿勢を大切にしましょう。
- 心構え1:「感謝」と「謙虚な姿勢」を忘れない
- あなたが産休・育休を取得している間、あなたの業務は誰かがカバーしてくれることになります。そのことへの感謝の気持ちと、「ご迷惑をおかけしますが」という謙虚な姿勢を忘れないようにしましょう。この気持ちが伝わるだけで、周囲の受け止め方は大きく変わります。
- 心構え2:今後の働き方は「相談する」姿勢で
- 「〇月から休みます」「復帰後は時短にします」と一方的に決定事項として伝えるのではなく、「〇月からお休みをいただきたいと考えているのですが、いかがでしょうか」「復帰後は時短勤務を希望しているのですが、可能でしょうか」というように、常に「相談する」姿勢を心がけましょう。この姿勢が、円滑なコミュニケーションと良好な関係構築に繋がります。
- 心構え3:体調は正直に伝え、無理をしない
- 妊娠中は、自分でも予測できない体調の変化が起こるものです。「迷惑をかけたくない」という気持ちから無理をしてしまうと、あなた自身と赤ちゃんの健康に影響を及ぼしかねません。辛い時は正直に体調を伝え、必要な配慮をお願いすることも、大切な仕事の一つです。あなたの健康が第一であることを忘れないでください。
5. 【報告後に】知っておくと安心!産休・育休の手続きと「保活」の始め方
職場への報告が終わったら、次はいよいよ具体的な手続きと、復職に向けた準備のスタートです。
1. 産休・育休制度の基本をおさらい(表で解説)
「産休」と「育休」は似ているようで異なる制度です。基本的な違いを理解しておきましょう。
| 制度名 | 正式名称 | 対象者 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 産休 | 産前産後休業 | 出産するすべての女性労働者 | 産前:出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から 産後:出産の翌日から8週間 |
| 育休 | 育児休業 | 1歳未満の子を養育する男女労働者(条件あり) | 原則、子どもが1歳になるまで(条件により最長2歳まで延長可) |
※詳細な取得条件は、会社の就業規則や人事・総務部にご確認ください。
2. 会社に提出が必要な書類リスト
産休・育休を取得するためには、会社への申請が必要です。一般的に、以下のような書類の提出を求められます。
- 産前産後休業取得者申出書
- 育児休業申出書
- 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
- 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
必要な書類や提出期限は会社によって異なるため、必ず人事・総務部に確認し、計画的に準備を進めましょう。
3. 育休後の復帰に必須!「保活」とは?
「保活」とは、子どもを保育園に入れるために行う活動全般を指します。
待機児童の問題は依然として多くの地域で深刻であり、育休後のスムーズな職場復帰には、妊娠中からの計画的な保活が不可欠です。「まだ生まれてもいないのに…」と思うかもしれませんが、人気の保育園はすぐに見学予約が埋まってしまうことも。体調の良い安定期から情報収集を始めるのがおすすめです。
4. 妊娠中から始める保活の第一歩【エンクルで園探し】
「保活って、何から始めたらいいの?」そんな不安を感じる方も多いはず。まずは、自宅や職場の近くにどんな保育園があるのかを知ることから始めましょう。
保育園探しサイト「エンクル」なら、スマホ一つで簡単に、あなたの希望に合った園探しから見学予約までをサポートします。
- STEP1:自宅の近くにある園を探す
地図や地域、こだわりの条件から、あなたのライフスタイルに合った保育園や幼稚園を簡単に検索できます。 - STEP2:気になる園を比較・検討する
気になる園を見つけたら、お気に入り登録。複数の園の基本情報や特色を一覧で比較検討できるので、効率的に候補を絞り込めます。 - STEP3:スマホから簡単に見学予約する
比較して候補が絞れたら、いよいよ見学です。「エンクル」なら、サイト上から直接、園の見学予約手続きが可能です。電話をかける手間なく、空いた時間にサッと予約できます。
6. 職場への妊娠報告に関するQ&A
最後に、職場への妊娠報告に関してよく寄せられる質問にお答えします。
1. Q. つわりがひどく、安定期前に休むことが増えそうです。どうすればいいですか?
A. 安定期を待たずに、まずは直属の上司に事情を説明し、相談しましょう。 母子の健康が最優先です。医師から指導があった場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」を提出することで、会社側は時差通勤や休憩時間の延長、業務内容の変更などの措置を講じる義務があります。
2. Q. 派遣社員や契約社員でも報告の仕方は同じですか?
A. 報告の基本的なマナーや準備することは同じです。 ただし、報告する相手が「派遣元(登録している派遣会社)」と「派遣先(実際に働いている職場)」の両方になります。まずは、雇用主である派遣元の担当者に相談し、派遣先の上司へ報告するタイミングや方法について指示を仰ぎましょう。
3. Q. 男性が育休を取得する場合の報告はどうすればいいですか?
A. 報告のタイミングや準備することは、女性の場合とほとんど同じです。 パートナーの出産予定日や、いつからいつまで育休を取得したいのかを明確にし、業務の引き継ぎなどを考慮して、できるだけ早めに(できれば1ヶ月以上前)直属の上司に相談することが大切です。「男性だから…」と遠慮せず、制度を積極的に活用しましょう。
4. Q. 報告後に不利益な扱い(マタハラ)を受けたらどうすればいいですか?
A. 妊娠・出産・育休の取得を理由とした解雇や減給、降格などの不利益な取り扱いは、男女雇用機会均等法で禁止されている「マタニティハラスメント(マタハラ)」にあたります。もし、そのような扱いを受けた場合は、一人で抱え込まず、社内のコンプライアンス窓口や人事部、労働組合、または外部の労働局などに相談してください。
まとめ:円満な妊娠報告で、安心してマタニティライフを迎えよう
この記事では、職場への妊娠報告のタイミングから具体的な伝え方、報告後の手続きまでを解説しました。
- 報告のタイミングは安定期(4〜5ヶ月頃)が目安
- 報告の順番は必ず「直属の上司」から
- 報告前に「出産予定日」や「希望の働き方」など5つの項目を準備しておく
- 報告の際は「感謝」と「相談する」姿勢を忘れない
- 報告後は速やかに手続きを進め、早めに「保活」をスタートする
職場への報告は、妊娠期間中の大きな山場の一つです。この記事を参考に、しっかりと準備をして臨めば、きっと職場からの理解と協力を得られるはずです。
職場への報告という大きなステップを終えたら、次は復職に向けた大切な準備、「保活」のスタートです。
あなたのマタニティライフと、その先のワーキングママライフが素晴らしいものになるよう応援しています。まずは「エンクル」で、お近くの保育園を検索することから始めてみませんか?
理想の保育園・幼稚園探しなら「エンクル」 検索して地図上で空き情報を一括比較!口コミや見学予約機能も。登録した希望条件でオファーも届く!
保育園探しはプロにお任せ!希望の園探しをトコトンお手伝いします!
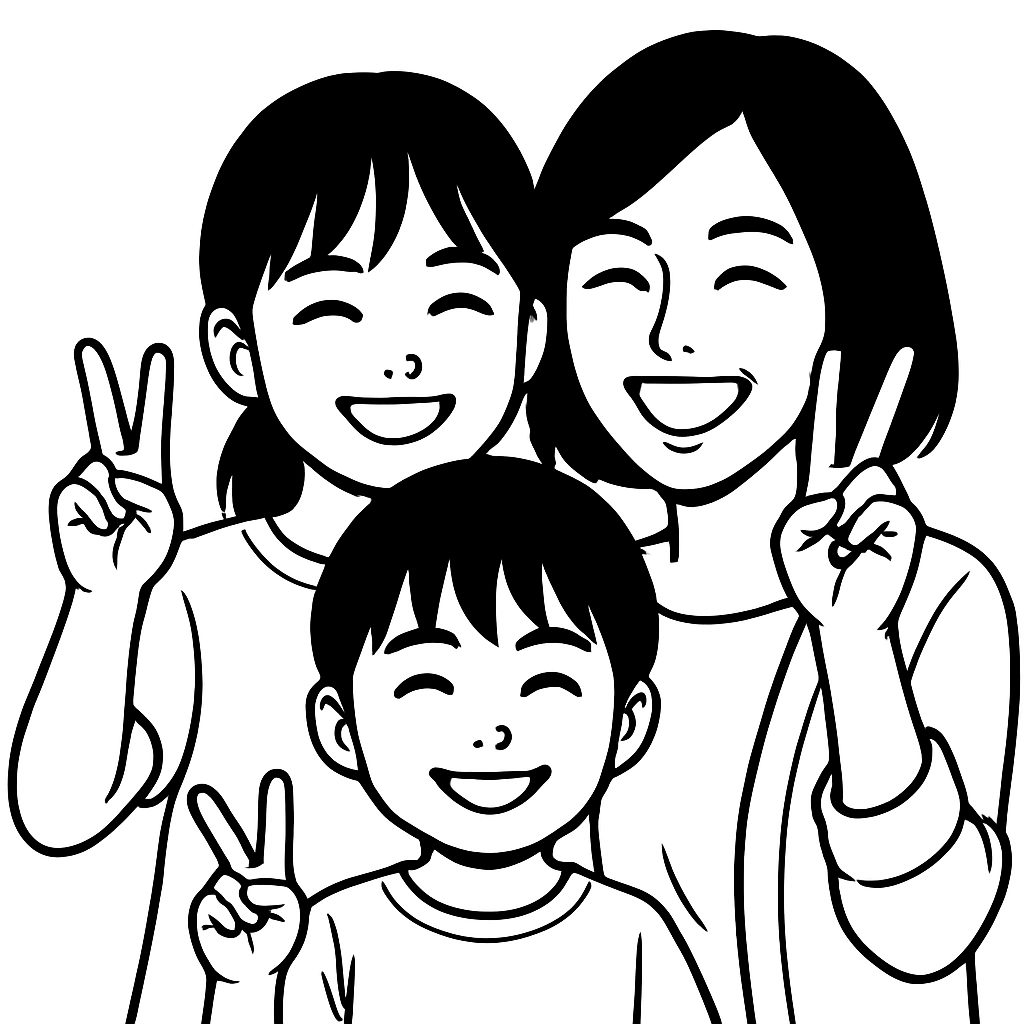
保活アドバイザーのもっちゃんです。小3の娘と年少の息子を育てる2児の母。保育園の転園を経験し、実体験をもとに保活&子育て情報を発信中。癒しは愛猫とのまったり時間です。








