![[安産祈願・お宮参り] 初穂料の書き方、これで完璧!封筒の選び方から金額、渡し方まで完全ガイド](/column/wp-content/uploads/2025/07/Image_fx-7-1.jpg)
お子さまの健やかな成長を願う安産祈願やお宮参り。準備を進める中で「初穂料(はつほりょう)」という言葉を目にし、「封筒の書き方は?」「いくら包めばいいの?」と不安に思っていませんか?
私も初めての安産祈願の準備をした時は、分からないことだらけで戸惑った経験があります。大切な儀式で恥ずかしい思いをしないよう、正しいマナーを知っておきたいですよね。
この記事では、初穂料を包む封筒(のし袋)の正しい書き方から、金額の相場、お札の入れ方、渡し方まで、写真付きで分かりやすく解説します。
これさえ読めば、初穂料に関するすべての疑問が解決し、自信を持って当日を迎えられます。
目次
- 1. そもそも初穂料とは?玉串料との違い
- 2. 【安産祈願・お宮参り】初穂料の金額相場はいくら?
- 3. 初穂料を包む封筒はどれ?のし袋の選び方
- 4. 【写真で解説】初穂料の封筒・のし袋の正しい書き方
- 5. 【図解】お金の入れ方・包み方のマナー
- 6. 当日の流れも確認!初穂料の渡し方マナー
- 7. これで安心!初穂料に関するよくある質問Q&A
- 8. まとめ:正しいマナーで心に残る素敵な一日に
1. そもそも初穂料とは?玉串料との違い
まずはじめに、「初穂料」がどのようなものなのか、よく似た言葉である「玉串料」との違いについて見ていきましょう。
1-1. 初穂料とは神社でのご祈祷に対する謝礼
初穂料とは、神社でご祈祷や祭祀をお願いする際に、神様への感謝の気持ちを込めてお供えするお金のことです。
その名の由来は、その年に初めて収穫されたお米(初穂)を神様にお供えしていた古くからの習わしにあります。時代とともにお米の代わりにお金をお供えするようになり、それが「初穂料」と呼ばれるようになりました。
1-2. 「玉串料(たまぐしりょう)」との違いは?どちらを使えばいい?
初穂料と似た言葉に「玉串料」があります。どちらも神様にお供えするお金という点では同じですが、少し意味合いが異なります。
| 種類 | 意味合い | 使える場面 |
|---|---|---|
| 初穂料 | 収穫への感謝が由来。お祝い事全般に使える。 | お祝い事(安産祈願、お宮参り、七五三、結婚式など) |
| 玉串料 | 神様に玉串(榊の枝)を捧げる代わりのお金。 | お祝い事、弔事の両方で使える。 |
安産祈願やお宮参りといったお祝い事では、どちらを使っても問題ありません。 しかし、「初穂料」がお祝いの意味合いが強い言葉なので、迷った場合は「初穂料」を選ぶと良いでしょう。
1-3. こんな場面で使います!初穂料が必要な行事一覧
初穂料は、安産祈願やお宮参り以外にも、人生の節目となる様々な行事で使われます。
- 安産祈願
- お宮参り
- お食い初め
- 七五三
- 厄払い・厄除け
- 合格祈願
- 地鎮祭
- 結婚式(神前式)
- お守りやお札を受けるとき
2. 【安産祈願・お宮参り】初穂料の金額相場はいくら?
次に、多くの方が気になる初穂料の金額についてです。いくら包めば良いのか、相場を確認しておきましょう。
2-1. 初穂料の相場は5,000円〜10,000円が一般的
初穂料の金額相場は、5,000円から10,000円が一般的です。
神社によっては、ご祈祷後にもらえる授与品(お札やお守りなど)の内容によって、複数のプランが用意されていることもあります。例えば、5,000円のプランと10,000円のプランがある、といった具合です。
2-2. 金額が「お気持ちで」とされている場合はどうする?
神社のホームページなどに金額の記載がなく、「お気持ちで」とされている場合もあります。このような時は、5,000円を包んでおけば失礼にあたることはないでしょう。 もし不安な場合は、予約の際に電話で直接問い合わせてみるのが確実です。
2-3. 事前に神社のホームページで確認するのが最も確実
最も確実な方法は、ご祈祷をお願いする神社のホームページで確認することです。「ご祈祷のご案内」といったページに、初穂料の金額が明記されていることがほとんどです。事前にチェックしておけば、当日慌てることなく安心です。
2-4. 初穂料は誰が払うべき?決まりはある?
「初穂料は誰が払うの?」という疑問もよく聞かれます。昔からの慣習では父方の祖父母が用意するケースもありましたが、現在では特に厳しい決まりはありません。
ご夫婦で支払う家庭が最も多いですが、両家の祖父母が「お祝いに」と申し出てくれることもあります。誰が支払うか、事前に家族で話し合っておくとスムーズです。
3. 初穂料を包む封筒はどれ?のし袋の選び方
初穂料は、のし袋に入れてお渡しするのがマナーです。どのようなのし袋を選べば良いのか、ポイントをご紹介します。
3-1. 【基本】水引が「紅白の蝶結び」の、のし袋を選ぶ
初穂料には、水引(みずひき)が「紅白の蝶結び」になっている、のし袋を選びましょう。
蝶結びは、何度でも結び直せることから、「何度あっても嬉しいお祝い事」に使われます。安産祈願やお子さまの成長を祝う行事にぴったりの水引です。
3-2. 「結び切り」や「あわじ結び」は使わないように注意
一方で、水引には「結び切り」や「あわじ結び」といった種類もあります。これらは一度結ぶとほどくのが難しい形をしているため、「一度きりであってほしいこと」に使われます。結婚祝いや快気祝い、弔事などで使われるものなので、安産祈願やお宮参りでは使わないように注意しましょう。
3-3. のし袋がない場合は「郵便番号欄のない白封筒」でも代用可能
もし、のし袋が手元にない場合は、郵便番号の記入欄がない真っ白な封筒で代用することも可能です。ただし、これはあくまで略式の方法です。できれば、きちんとのし袋を用意するのが望ましいでしょう。
3-4. のし袋はどこで買える?
のし袋は、以下のような場所で購入できます。
- 文房具店
- スーパーマーケット
- コンビニエンスストア
- 100円ショップ
- 書店
- デパート
4. 初穂料の封筒・のし袋の正しい書き方
4-1. 準備するもの:濃い黒の筆ペンか毛筆
文字を書く際は、濃い黒色の筆ペンか毛筆を使いましょう。 ボールペンや万年筆、薄墨のペンはマナー違反となるため避けてください。筆ペンが一本あると、今後の冠婚葬祭でも役立つのでおすすめです。
4-2. ①表書き(上段)の書き方:「御初穂料」または「初穂料」
のし袋の上段中央には、お金の目的を示す「表書き」を書きます。
「御初穂料」と書くのが最も丁寧な書き方です。 もちろん、「初穂料」と書いても問題ありません。水引にかからないよう、バランス良く書きましょう。
4-3. ②表書き(下段)の書き方:赤ちゃんの名前?夫婦連名?
下段には、ご祈祷を受ける人の名前を書きます。ここは、安産祈願とお宮参り・七五三で書き方が異なるので注意が必要です。
- 安産祈願の場合:夫婦の連名
- 安産祈願のご祈祷は、お腹の赤ちゃんのためだけでなく、お母さんのためでもあります。そのため、ご夫婦の氏名を連名で書きます。
- お宮参り・七五三の場合:お子さまの名前(ふりがなも忘れずに)
- お宮参りや七五三は、お子さまの成長を感謝し、今後の健やかな成長を願う儀式です。そのため、中央にお子さまのフルネームを書きます。
神社の方が読みやすいように、名前の右側にふりがなを振っておくと、より丁寧な印象になります。
4-4. ③中袋(表面)の書き方:包んだ金額を「大字(だいじ)」で書く
中袋(または中包み)の表面には、包んだ金額を記入します。このとき、算用数字(1, 2, 3…)ではなく、「大字(だいじ)」と呼ばれる旧字体の漢数字を使うのが正式なマナーです。これは、後から金額を改ざんされるのを防ぐためです。
金額の書き方見本(例:金伍仟圓、金壱萬圓)
| 包んだ金額 | 大字での書き方 |
|---|---|
| 5,000円 | 金伍仟圓 または 金五千円 |
| 7,000円 | 金七阡円 または 金七千円 |
| 10,000円 | 金壱萬圓 または 金一万円 |
先頭に「金」を、末尾に「圓」または「円」をつけます。
4-5. ④中袋(裏面)の書き方:住所と名前を書く
中袋の裏面の左下には、あなたの住所と氏名を書きます。
これは、神社側がどなたからの初穂料かを管理しやすくするための配慮です。郵便番号も忘れずに書きましょう。
4-6. 【白封筒の場合】表と裏の書き方
のし袋の代わりに白封筒を使う場合は、以下のように書きます。
- 表面
- 上段中央に「御初穂料」
- 下段中央に祈祷を受ける方の氏名(安産祈願なら夫婦連名、お宮参りならお子さまの名前)
- 裏面
- 左下に包んだ金額(例:金壱萬圓)
- さらにその左に住所と氏名
5. お金の入れ方・包み方のマナー
お金の入れ方にも、守るべきマナーがあります。
5-1. お札は新札(ピン札)を用意するのが望ましい?
必ずしも新札である必要はありませんが、感謝の気持ちを表すために、できるだけシワや汚れのない綺麗なお札を用意するのが望ましいです。もし新札が用意できなくても、折り目の少ない綺麗なお札を選んで包みましょう。
5-2. お札の向きは?肖像画が表側・上に来るように揃える
お札を中袋に入れる際は、向きを揃えるのがマナーです。
すべてのお札の肖像画(顔)が、中袋の表面のほうを向くようにし、さらに肖像画が上に来るようにして入れます。 こうすることで、袋から出したときに肖像画が最初に見えるようになります。
5-3. 中袋への入れ方と上袋のたたみ方
お金を中袋に入れたら、上袋(外側の包み)で包みます。
上袋の裏側の折り返しは、下側の折り返しを先にたたみ、その上に上側の折り返しを重ねます。 これには「幸せが下にこぼれ落ちず、溜まりますように」という願いが込められています。
6. 当日の流れも確認!初穂料の渡し方マナー
最後に、当日の初穂料の渡し方についてです。スマートにお渡しできるよう、流れをシミュレーションしておきましょう。
6-1. 渡すタイミングはご祈祷の受付時
初穂料は、ご祈祷の申し込みをする受付のタイミングでお渡しするのが一般的です。社務所や授与所などで受付をする際に、「本日はご祈祷をお願いいたします」と挨拶しながらお渡ししましょう。
6-2. 袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが丁寧な作法
のし袋をそのままバッグから出すのではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが最も丁寧な作法です。袱紗は、のし袋が汚れたり、水引が崩れたりするのを防ぐ役割があります。
受付で渡す直前に袱紗から取り出し、相手が表書きを読める向きにして、両手で丁寧にお渡しします。もし袱紗がない場合は、綺麗なハンカチで代用しても良いでしょう。
6-3. 渡す際の一言「本日はよろしくお願いいたします」
お渡しする際は、無言で差し出すのではなく、一言添えるのがマナーです。
「本日は、安産祈願(お宮参り)のご祈祷をよろしくお願いいたします。こちら、御初穂料でございます。」
このように挨拶をしながらお渡しすると、より気持ちが伝わります。
7. これで安心!初穂料に関するよくある質問Q&A
ここでは、初穂料に関してよく寄せられる質問にお答えします。
- Q. ボールペンや万年筆で書いてもいいですか?
- A. いいえ、筆ペンか毛筆で書くのが正式なマナーです。
ボールペンや万年筆は事務的な筆記用具とされているため、神様への感謝を表す初穂料の表書きにはふさわしくないとされています。濃い黒の筆ペンを使用しましょう。 - Q. 中袋がないタイプののし袋はどうすればいいですか?
- A. のし袋の裏面の左下に、直接、住所と金額を書きましょう。
金額は表面に書かないように注意してください。金額の書き方は、中袋がある場合と同様に大字で書くのが丁寧です。 - Q. 兄弟(姉妹)一緒にお参りする場合の初穂料はどうなりますか?
- A. 基本的には、お子さま一人ひとりに対して初穂料を用意します。
ただし、神社によっては「ご兄弟(姉妹)で一袋にまとめていただいて結構です」と言われることもあります。事前に神社に確認するのが最も確実です。
まとめて包む場合の金額は、単純に2倍にするか、1.5倍程度の金額(例:一人5,000円なら二人で7,000円か10,000円)を包むことが多いようです。表書きの下段には、お子さまたちの名前を連名で書きましょう。
8. まとめ:正しいマナーで心に残る素敵な一日に
今回は、安産祈願やお宮参りで必要となる初穂料について、封筒の選び方から書き方、渡し方まで詳しく解説しました。
- 初穂料とは、神社でのご祈祷に対する感謝の気持ち
- 金額の相場は5,000円〜10,000円が一般的
- のし袋は「紅白の蝶結び」の水引がついたものを選ぶ
- 表書きは筆ペンを使い、「御初穂料」と書く
- 名前は安産祈願なら夫婦連名、お宮参りならお子さまの名前を書く
- お金は綺麗なお札を用意し、向きを揃えて入れる
- 渡すときは袱紗に包んで持参し、受付で丁寧にお渡しする
初めての儀式は何かと準備が大変で、不安に感じることも多いかもしれません。ですが、一つひとつ心を込めて準備をすることで、その日はきっと忘れられない素敵な思い出になるはずです。
この記事が、あなたの不安を少しでも解消する手助けとなれば幸いです。お子さまの健やかなご成長を、心からお祈りしております。
理想の保育園・幼稚園探しなら「エンクル」 検索して地図上で空き情報を一括比較!口コミや見学予約機能も。登録した希望条件でオファーも届く!
保育園探しはプロにお任せ!希望の園探しをトコトンお手伝いします!
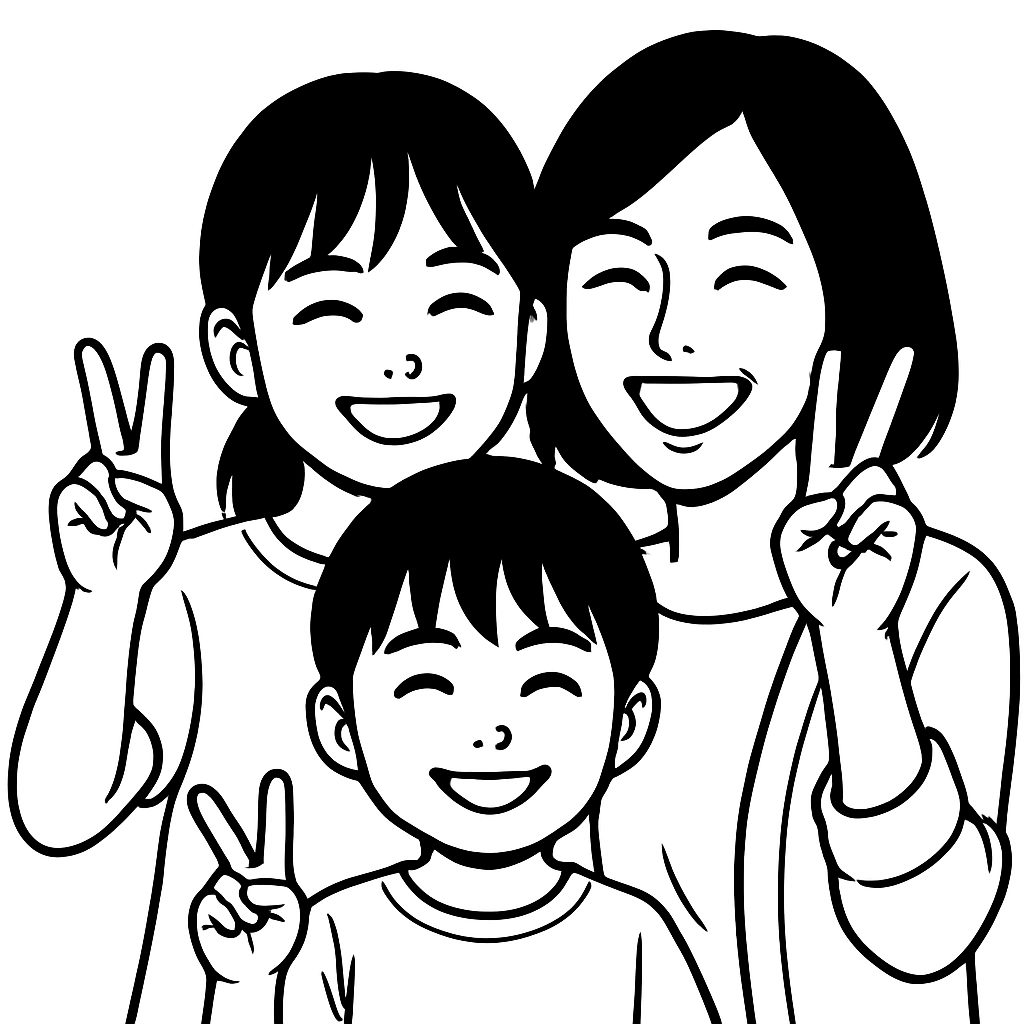
保活アドバイザーのもっちゃんです。小3の娘と年少の息子を育てる2児の母。保育園の転園を経験し、実体験をもとに保活&子育て情報を発信中。癒しは愛猫とのまったり時間です。
![[安産祈願・お宮参り] 初穂料の書き方、これで完璧!封筒の選び方から金額、渡し方まで完全ガイド](/column/wp-content/uploads/2025/07/Image_fx-7-1-730x410.jpg)








